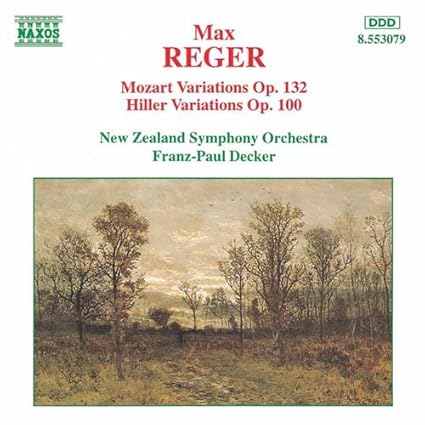①コルンゴルド:ヴァイオリン協奏曲ニ長調 作品35
②ブリテン:ヴァイオリン協奏曲 作品15
ヴィルデ・フラング(V) ジェイムズガフィガン指揮 フランクフルト放送交響楽団
全くヴァイオリニストのことは知らずにただ収録されている作品に興味が湧いたので購入した盤。①はハイフェッツを始め、その時代のヴィルトーゾが取り上げてきたもの。コルンゴルドが音楽を提供したハリウッドの映画作品から転用された素材で構成されたもの。冒頭は「乞食王子」のタイトルバックで始まる。とにかく華やいだ音楽ではる。ムターに師事したこの若い女流奏者はいともたやすく弾きこなす。②の方は初演の奏者がたやすく弾いたのが気に入らずに改訂した作品ということで有名。ブリテンの性格の悪さみたいものを反映したいわくつきの作品。これも難なくこの奏者は弾くのはやはり時代の進歩とみるべきか。