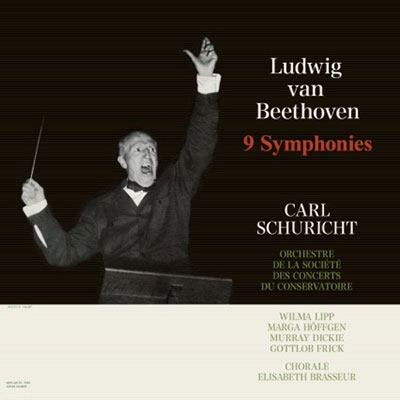ブラームス:
[CD1]交響曲第1番ハ短調Op.68,
[CD2]交響曲第2番ニ長調Op.73,
[CD3]交響曲第3番ヘ長調Op.90, ハイドンの主題による変奏曲Op.56a,
[CD4]交響曲第4番ホ短調Op.98,
[CD5]ピアノ協奏曲第1番ニ短調Op.15,
[CD6]ピアノ協奏曲第2番変ロ長調Op.83,
[CD7]ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.77,
[CD8]ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲イ短調Op.102, 大学祝典序曲Op.80
【演奏】
ズービン・メータ(指揮) ニューヨーク・フィルハーモニック,
ダニエル・バレンボイム(ピアノ:CD5&6),
アイザック・スターン(ヴァイオリン:CD7),
ピンカス・ズカーマン(ヴァイオリン:CD8),
リン・ハレル(チェロ:CD8)
【録音】
1978~1982年、ニューヨーク
[CD1]交響曲第1番ハ短調Op.68,
[CD2]交響曲第2番ニ長調Op.73,
[CD3]交響曲第3番ヘ長調Op.90, ハイドンの主題による変奏曲Op.56a,
[CD4]交響曲第4番ホ短調Op.98,
[CD5]ピアノ協奏曲第1番ニ短調Op.15,
[CD6]ピアノ協奏曲第2番変ロ長調Op.83,
[CD7]ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.77,
[CD8]ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲イ短調Op.102, 大学祝典序曲Op.80
【演奏】
ズービン・メータ(指揮) ニューヨーク・フィルハーモニック,
ダニエル・バレンボイム(ピアノ:CD5&6),
アイザック・スターン(ヴァイオリン:CD7),
ピンカス・ズカーマン(ヴァイオリン:CD8),
リン・ハレル(チェロ:CD8)
【録音】
1978~1982年、ニューヨーク
ズービン・メータがNYPの音楽監督時代に米コロムビアに入れたブラームスの全集である。アナログ録音の末期のものだが、驚くことに4つの交響曲はこれが初めてCDとして発売されたものという。しかも第1番に至ってはLPの発売はなく、カセットテープのみ販売というからもっと驚く。発売元の説明では、同じような時期にVPOを振ってデッカに録音して発売が先行していて、契約上の関係でLPは発売されなかったという。全てビジネス上での問題ではある。協奏曲の方は単独でもカタログでは見かけるもの。
さて、どんな解釈か。インパクトはあまりないが、第4番は他の指揮者に比べてポルタメントを強調したりするし、第1番はテンポをやや動かすようなところがあるが、これらがそんなに効果は上がってないように思える。ブラームスの交響曲は競合の多い分野だが、どちらかというと地味な存在。したがってCBSもCDにはなかなかしにくかったのかもしれない。第1番は件のデッカ盤と比べてみるのも一興であろうが、残念ながら持っていない。