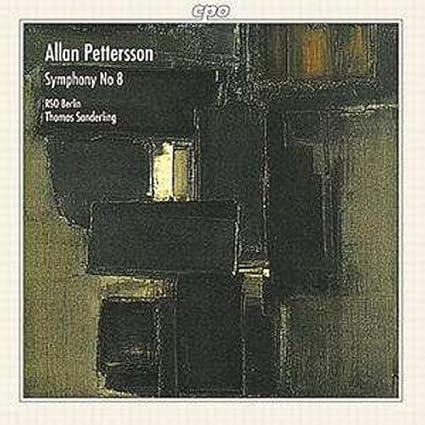November 27, 2015, 4:53 pm
【曲目】
《CD1…8.572396》1-4.交響曲 第1番 ヘ短調 Op.10(1924-1925)/5-10.交響曲 第3番 変ホ長調「メーデー」Op.20(1929)
《CD2…8.572708》1-3.交響曲 第2番 ロ長調「十月革命に捧ぐ」Op.14/4-7.交響曲 第15番 イ長調 Op.141
《CD3…8.573188》1-3.交響曲 第4番 ハ短調 Op.43
《CD4…8.572167》1-4.交響曲 第5番 ニ短調 Op.47/5-9.交響曲 第9番 変ホ長調 Op.70
《CD5…8.572658》1-3.交響曲 第6番 ロ短調 Op.54/4-7.交響曲 第12番 ニ短調「1917年」Op.112
《CD6…8.573057》1-4.交響曲 第7番 ハ長調「レニングラード」Op.60
《CD7…8.572392》1-5.交響曲 第8番 ハ短調 Op.65
《CD8…8.572461》1-4.交響曲 第10番 ホ短調 Op.93
《CD9…8.572082》1-4.交響曲 第11番 ト短調「1905年」Op.103
《CD10…8.573218》1-5.交響曲 第13番 変ロ短調「バビ・ヤール」Op.113
《CD11…8.573132》1-11.交響曲 第14番 ト短調「死者の歌」Op.135
【演奏】
アレクサンドル・ヴィノグラードフ(バス)…CD10.11
ガル・ジェイムズ(ソプラノ)…CD11
ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー合唱団…CD1.5-7;2.1-3
ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー合唱団男声セクション…CD10
ハダースフィールド合唱協会…CD10
ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団
ヴァシリー・ペトレンコ(指揮)
今更ながらの全集である。既にバルシャイ、コンドラシン、ゲルギエフのものが手許にあるし、ヤンソンスも単売品で全曲揃っている。他にムラヴィンスキーやオーマンディ、バーンスタインもあったりするし、単売で曲によってはいろいろ持っているのに、また購入してしまった。
ヴァシリー・ペトレンコは1976年生まれの指揮者というから、まだ若い。その分突進力があり活きがいい。ただ、相手がイギリスのRLPOなので、爆演はない。RLPOはグローヴスなどの指揮によるディーリアスで知ったオーケストラなので、極めてノーブルな音を出す。それでもペトレンコは鳴るところは鳴らせているので、バランスの取れた演奏になっていると思う。これは単売されたものをBOX化して、更に一枚あたりの単価を下げての販売のようだ。
↧
November 28, 2015, 5:11 am
ブルックナー:交響曲第7番ホ長調(改訂版)
ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 ケルン放送交響楽団
1963年5月10日 ケルンでのライヴ
クナの同曲の録音はVPOでの1949年のザルツブルク音楽祭での実況があるが、これは最晩年のライヴで使用楽譜は49年のものと同一という。プレーヤーにかけてみると、モノラルながら響が意外と豊饒で立体感も覚えるものだった。これは正規の放送音源のものかもしれない。
1963年と言えば、この指揮者の死の2年前。既にウィーン藝術週間の1962~3年の映像が出ているが、同じよう感じで舞台に上がっていたのだろうと思う。前半の二つの楽章は意外とあっさりして、速めのテンポ。しかし、何か聴いていてもたれなくてさわやかな感じはする。ただ、最終楽章になるとオーケストラのメンバーもかなり疲労感があるのか、ミスも目立つ。しかし、この思わぬ響きに拾い物をしたお得感みたいなものを覚えた。
↧
↧
November 29, 2015, 12:44 am
【曲目】
《CD1》
1-4. 交響曲第1番(37'39)
5-8. 交響曲第2番(43'12)
《CD2》
1-3. 交響曲第3番(28'17)
4-7. 交響曲第4番(36'50)
《CD3》
1-3. 交響曲第5番(30'32)
《CD4》
1-4. 交響曲第6番(29'13)
5-8. 交響曲第7番(21'48)
《Disc1:ブルーレイ・ディスク・オーディオ》
交響曲第1-7番(24bit/96kHz)
2.0 PCM Stereo 24bit/96kHz
5.0 DTS-HD MA 24bit/96kHz
227分
[ボーナス・ビデオ]
サー・サイモン・ラトル、シベリウスを語る(ドイツ語字幕のみ)
58分
《Disc2:ブルーレイ・ディスク・ビデオ》
交響曲第1-7番(HD Video)
画面:Full HD 1080/60i 16:9
音声:2.0 PCM Stereo、5.0 DTS-HD MA
リージョン:All
297分
[ボーナス・ビデオ]
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団のデジタル・コンサート・ホールについて
【演奏】
サー・サイモン・ラトル(指揮)
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
【録音/収録】
CD&BDA:
2014年12月18-20日(5番)
2015年1月28日~2月6日(1~4番)
2015年2月7~9日(5~7番)
VIDEO:
2015年2月6日(1、2番)
2015年2月7日(3、4番)
2015年2月8日(5~7番)
録音場所:フィルハーモニー、ベルリン
[24bit/192kHz録音]
ベルリン・フィルの自主製作盤によるラトルとのシベリウス交響曲全集。音だけでなく映像もついたBOXになっており、録音だけと映像ものとは違う演奏であることがポイントでもある。また、日本語解説の冊子もついていて、これもありがたい。オーケストラのメンバー表もあって、日本人もコンマスの樫本大進も含めて数人いることも確認できる。そして、このオーケストラが7曲をいつ初めて演奏したかも、書いてあって、第3番は2010年にラトルが指揮したのが最初というにが驚く。かのカラヤン御大が全ては演奏せず、録音も全集が完結していないことは知っていたが、BPO自体も今世紀に入って初めて演奏しているのは意外でもあった。ラトルもインタビューで驚いたと言っている。
さて、イギリス出身のラトルだから、シベリウスの交響曲は若い頃から馴染みがあるし、すでにEMIにも全集をものにしている。やや、せっかちな部分はあるものの、若々しく気持ちのいい演奏を展開してくれる。この記事を書いた段階では、CDのみの鑑賞。映像のBDは後刻鑑賞するつもりだ。映像があるとまた違った印象になるのかもしれない。CDと同じ音源のBD-Audioはその後ということにしている。こういうセットが良いのかはわからないが、BOXがちょっとユニークなので収納場所に、正直なところ困っている。
↧
November 29, 2015, 9:08 pm
【曲目】
シュトラウス:歌劇「エレクトラ」全曲
【演奏】
カルロス・クライバー指揮コヴェントガーデン王立歌劇場管、合唱団、マルタ・シルメイ、ビルギット・ニルソン、グィネス・ジョーンズ、チャールズ・クレイグ、ドナルド・マキンタイア
【録音】
1977年5月14日ライヴ
以前にも出ていたそうだが、今回は音質改善での再登場という。既にドイツでのライヴ盤もあって、二種類目の登場だが、コヴェントガーデン王立歌劇場のアンサンブルというのが目を惹く。ただし、レパートリーの絞り込みで晩年には、外された作品となったようである。
録音はやや歌唱が遠目に入っているが、耳が慣れてくると違和感なく聴けてしまう。多少スクラッチノイズみたいなものは聴こえるが、鑑賞に支障はない。途中唐突に切れて2枚目になるののだが、切れ目をもう少し丁寧にして欲しかった。クライバーが何故外したのかはわからない。演目の内容がややショッキングなところが気に入らなかったのかもしれない。タイトルロールはビルギット・ニルソン。こうした音質の乏しいものでも、突き抜けて聴こえてくるのは、やはり並大抵の歌手ではなかったということだと思う。
↧
December 1, 2015, 4:02 am
マリア・カラス/アット・コヴェント・ガーデン1962&64
マリア・カラスがロンドンのコヴェントガーデン王立歌劇場に1962年と1964年に出演した際のライヴ映像の組み合わせ。1962年のジョルジュ・プレートル指揮によるリサイタル映像は『ドン・カルロ』の壮大で悲劇的なアリア「世の空しさを知る神」と、『カルメン』の抜粋。
1964年の『トスカ』は、イタリアのオペラ指揮者、カルロ・フェリーチェ・チラーリオの指揮でおこなわれた第2幕の舞台映像。この『トスカ』は、直前の全曲上演とは別にBBCによるテレビ放送用のため第2幕のみ上演されたというもので、演出は映画監督フランコ・ゼッフィレッリというのも実に豪華。
今回のブルー・レイ化のために、アビー・ロード・スタジオで音声のリマスターがおこなわれ、画面も1080i HDにアップコンバートされて見やすくなっているということです。(HMV)
【収録情報】
● ヴェルディ:歌劇『ドン・カルロ』より『世の空しさを知る神』
● ビゼー:歌劇『カルメン』より前奏曲、『ハバネラ』、第3幕への間奏曲、『セギディーリャ』
マリア・カラス(ソプラノ)
コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団&合唱団
ジョルジュ・プレートル(指揮)
収録:1962年11月4日(ライヴ)
● プッチーニ:歌劇『トスカ』より第2幕
演出:フランコ・ゼッフィレッリ
マリア・カラス(トスカ)
ティト・ゴッビ(スカルピア)
レナート・チオーニ(カヴァラドッシ)
ロバート・バウマン(スポレッタ)
デニス・ウィックス(シャルローネ)
コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団&合唱団
カルロ・フェリーチェ・チラーリオ(指揮)
収録:1964年2月9日(ライヴ)
収録時間:70分
画面:モノクロ、4:3、1080i HD
字幕:なし
Region All
こんな映像が出てくるとは、やはり人気があるからだろう。しかもステレオ音声である。少々割れ気味だが、この歌手のオペラの所作がモノクロながら、見ることができるのは貴重である。「トスカ」第2幕は、テレビ用に撮られたもので、上演途中の拍手もないのは観客はいなかったのかもしれない。最後に観客が映るが編集によるのではないかと思ってしまう。いや、途中では拍手しないようにBBCが観客に求めたのかもしれない。有名なアリア「歌に生き、恋に生き」の後に拍手がないのは、少し拍子抜けがする。
「トスカ」はタイトルロールよりは敵役のスカルピアが中心だ。その憎々しい存在は相当な演技力もいる。ティト・ゴッピはまさにうってつけで、この人の演技も目にできるのはやはりうれしい。東京での「オテロ」のイヤーゴも素晴らしいが、こちらもいいのだ。部分的なのが惜しいが、貴重なものを見せてもらえてうれしい限りだ。
↧
↧
December 3, 2015, 5:22 pm
【曲目】
ショスタコーヴィチ(1906-1975):
交響曲第4番ハ短調 Op.43(1935-1936)(*)
交響曲第13番「バビ・ヤール」(バス独唱、バス合唱と管弦楽のための)Op.113(1962)(+)
【演奏】
ヴィタリー・グロマツキー(バス(+))
ロシア共和国合唱団バス・グループ(+)
アレクサンドル・ユルロフ(合唱指揮(+))
モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団
キリル・コンドラシン(指揮)
【録音】
1961年12月30日(*)、1962年12月18日(+)、ライヴ、モスクワ音楽院大ホール、モスクワ、ロシア、ソヴィエト、モノラル
初演時の録音がやはりあったということだ。後者の曲はその2日後の公演の録音もある。いずれも当時の当局からすれば、好ましからざる作品の演奏で、いろいろ圧力はあったとは聴いている。だから録音媒体の記録は、最悪の場合は破棄される危険性もあったのではなかろうか。
コンドラシンと作曲者の執念があったのかもしれない。後年、体制に近いと思われていたコンドラシンが西側へ亡命したのは、こうした反体制的行為が伏線だったのではなかろうか。演奏もさることながら、歴史的瞬間の記録でもある。
録音はモノラルだが、鑑賞には何ら支障はない。むしろスッキリした感じに聴こえる。ただ現物が届いてびっくりしたのは、オーケストラの名称だ。通販のカタログにも単に「モスクワ・フィル」としか書いていない。ところが、第4番は「The Moscow Region Philharmonic Orchestra」、第13番は「The Moscow Philharmonic Orchestra」とある。わずかに1年の間に名称を変更したのか、違う団体なのか、判断材料が自分にはない。ロシアのオーケストラは同じような名称のものが複数存在していて複雑ということは知っていたが。
↧
December 4, 2015, 12:32 am
『プッチーニ:歌劇《トゥーランドット》(F.アルファーノ補筆版)』
【演奏】
トゥーランドット・・・リセ・リンドストローム(S)/カラフ・・・マルコ・ベルティ(T)/リュー・・・中村恵理(S)/ピン・・・ディオニュシオス・ソルビス(Br)/ポン・・・ダグラス・ジョーンズ(T)/パン・・・デヴィッド・バット・フィリップ(T)/皇帝アルトゥーム・・・アラスディア・エリオット(T)/ティムール・・・レイモンド・アセト(B) 他/ロイヤル・オペラ合唱団(合唱指揮・・・レナート・バルサドンナ)/ロイヤル・オペラ・ハウス管弦楽団/ヘンリク・ナナシ(指揮)/アンドレイ・セルバン(演出)/アンドリュー・シンクレア(リバイバル演出)/サリー・ジェイコブス(装置・デザイン)/F.ミッチェル・ダーナ(照明デザイン)/ケイト・フラット(コレオグラフィ)/タティアナ・ノバエス=コエロー(コレオロジスト)
【録音】
2014年9月 ロイヤル・オペラ・ハウス ライヴ
何かムキになって、この演目を集めているような気がしてきた。2種類のMET、ザルツブルク、ウィーンなどの映像があるにも拘わらず、また手を出してしまった。一つにはリューが日本のソプラノの中村恵理がやっていることも惹かれたかもしれない。
初演指揮のトスカニーニは初日はアルファーノが補筆した部分を演奏しなかったことは有名である。「ここで作曲者は筆を置いた」と聴衆に向かって、語ったと言われる。かれはアルファーノの部分が気に入らなかったことも知られている。それで彼はかなりその部分をカットしたようで、それが慣例化になったということも何かで読んだことがある。確かにリューの死の直後からは、途端に腰折れのように輝きは失われているのは確かだが、トスカニーニによるカットで劇の展開もわかりづらくなっているのこともあるかもしれない。今もプッチーニが筆を止めたところで幕にしてしまった方が良いように思うのは、私だけだろうか。
この映像で面白いのは、舞台裏のバンドの奏者は極めてラフな服装で本番を演奏しているようだし、ピット内では作曲者の指定通り、コントラバス・トロンボーンが使用されていることも確認できた。
↧
December 12, 2015, 5:19 pm
案内役はルネ・フレミング。舞台裏も出てくるが、好みとしてあまり目にしたくない。最初はスタンバイの風景が出てくる。この映像で注目はフレミングのコメントにもあるが、レヴァインの復帰である。ただ、もう歩行は困難なのだろうか、指揮台のところがエレベーターになってきて、座ったままで登場だ。したがって、健常という訳ではないようでやはり痛々しい。レヴァインはこの作品が得意なようで、音楽は以前の公演映像同様に音楽は活き活きしているのは救いである。 演出は、やはり読み替えで中世ではなく、20世紀初頭頃に移している。
![]() ヴェルディ:『ファルスタッフ』全曲
ヴェルディ:『ファルスタッフ』全曲
レヴァイン&メトロポリタン歌劇場管弦楽団&合唱団(2013)
マエストリ、ミード、ファナーレ、ほか
ムーティ&スカラ座、メータ&ウィーン、バッティストーニ&パルマ、ガッティ&チューリヒの『ファルスタッフ』で見事な演技を披露していたスペシャリスト、アンブロージョ・マエストリが、メトの舞台でロバート・カーセンの生き生きとした演出によって歌いあげた話題の舞台を、ライヴ・ビューイングの技術で収録した映像作品。
ドタバタ喜劇の中に、ロマンスやファンタジーも巧みに盛り込まれたこの作品は、オーケストラ・パートが充実していることでも知られていますが、レヴァインだけにそちらの面も万全です。また、若い恋人たちのロマンスを担うフェントン役に、イタリア語講座で話題になり、来日公演も評判となった若手テノール、パオロ・ファナーレが出演しているのも注目されるところです。(HMV)
【収録情報】
● ヴェルディ:歌劇『ファルスタッフ』全曲
アンブロージョ・マエストリ(ファルスタッフ)
ステファニー・ブライズ(クイックリー夫人)
アンジェラ・ミード(アリーチェ)
リゼット・オロペーサ(ナンネッタ)
ジェニファー・ジョンソン・カーノ(メグ・ペイジ)
パオロ・ファナーレ(フェントン)
フランコ・ヴァッサッロ(フォード)
メトロポリタン歌劇場管弦楽団&合唱団
ジェイムズ・レヴァイン(指揮)
ロバート・カーセン(演出)ポール・スタインバーグ(美術) ブリギッテ・ライフェンシュトゥール(衣装)
収録時期:2013年12月14日
収録場所:メトロポリタン歌劇場(ライヴ)..
![]()
↧
December 12, 2015, 5:38 pm
これは忠臣蔵外伝の一つ。俵星玄蕃と杉野十平次の物語である。三波春夫の浪曲歌謡などでも知られる話ではある。通常の「忠臣蔵」ではあまり触れられない、四十七士同士の階級格差とか、差別意識とかが、クローズアップされることが多いような気がする。大川橋蔵扮する杉野は、剣術や槍など武芸が今一つの下級武士。仲間に散々ばかにされて、男妾が妥当とさえ言われる始末だ。槍の名手、俵星玄蕃(片岡千恵蔵)に弟子入りする....、といった内容だ。
中味はほぼ講談的内容だが、仲間の蔑視がかなり強烈に描かれていて、それが強く印象に残るのである。ことに武林惟七(若山富三郎)の「イジメ」は強烈だった。
↧
↧
December 12, 2015, 5:55 pm
これは、吉永小百合が映画デビューした作品として、文献的には有名だった。しかし、実際の映画を観る機会はなかなかなかった作品でもあった。
1時間くらいの中篇といったところで、おそらく添え物として公開されたようではあるし、監督の生駒千里もあまりよく知らない人だった。監督の登竜門として試験的に撮らせたものかもしれない。中味は勤労青少年の苦労話で、後年の「キューポラのある街」に近いものだ。吉永小百合は、主人公の少年を励ます顧客の娘役で登場する。まだ14歳で中学生だが、役柄も女生徒役の登場だ。まだ、十束一絡の扱いで子役の一人にすぎない。映画として可まおなく不可もなくといったところか。
↧
December 14, 2015, 4:40 pm
収録情報】
● オッフェンバック:喜歌劇『美しきエレーヌ』全曲
エレーヌ:
ジェニファー・ラーモア(ソプラノ)
パリス:ハン・サンジュン(テノール)
メネラウス:ペーター・ガイヤール(テノール)
アガメムノン:ヴィクトール・ラド(バリトン)
オレスト::レベッカ・ジョー・ローブ(メゾ・ソプラノ)
カルカス:クリスティアン・ミードル(バス)
バッキス:アナト・エドリ(ソプラノ)
ハンブルク国立歌劇場合唱団(合唱指揮:エーベルハルト・フリードリヒ)
ハンブルク国立フィルハーモニー管弦楽団
ゲーリット・プリースニッツ(指揮)
演出:ルノー・ドゥーセ
舞台・衣装:アンドレ・バーベ
照明:ギイ・シマール
ドラマトゥルク:ケルスティン・シュスラー=バッハ
収録時期:2014年
収録場所:ハンブルク歌劇場(ライヴ)
オッフェンバックの神話に基づいたオペレッタ。日本ではあまり馴染みはないのかもしれないが、この盤が初めての映像化ではない。ミンコフスキーによるパリの上演映像も以前出ていた。ヨーロッパでは人気演目なのかもしれない。とてもユーモラスで楽しい舞台ではある。ただし、これは神話どころか、現代のクルーズ船が舞台で極めて世俗的な舞台に変容している。そこまでやっていいのかと思うほではあるが、日本人である自分と向こうの人たちの感覚はまったく違うことを思い知らされる。
これには輸入盤ながら日本語字幕が付いているので、ありがたい。
↧
December 14, 2015, 5:06 pm
![]()
収録内容】
イストミンは、スターンとの二重奏やトリオで有名で、室内楽奏者としての卓越した手腕が高く評価され、数多くのレコーディングもおこなわれましたが、当ボックスでは、これまであまりクローズアップされてこなかったソリストとしてのイストミンのレコーディングを数多く収録しています。
19歳の時にアドルフ・ブッシュと共演したバッハのピアノ協奏曲第1番に始まり、パブロ・カザルスと共演したバッハのブランデンブルク協奏曲第5番(ヴァイオリンはシゲティ)、モーツァルトのピアノ協奏曲第14番、ショパンの夜想曲全曲、ブラームスのヘンデル・ヴァリエーションなどのモノラル期の演奏は、若きイストミンの才能を刻印しています。ユージン・オーマンディ指揮フィラデルフィア管弦楽団との共演では、ベートーヴェン第4番、第5番『皇帝』、ショパン第2番、ブラームス第2番、チャイコフスキー第1番、ラフマニノフ第2番が収録されており、シューマンのピアノ協奏曲では最晩年のブルーノ・ワルター指揮コロンビア交響楽団が花を添えています。
さらに注目されるのは、ディスク11~12に収録された世界初発売となる音源10曲で、イストミン絶頂期のピアニズムを堪能することができます。
【ユージン・イストミン・バイオグラフィ】
1925年11月26日、ニューヨーク生まれ。両親はナイトクラブの歌手だったロシア人。アレクサンダー・ジロティの娘、クリエナ・ジロティにピアノを学ぶ。12歳でカーティス音楽学校に入学し、ルドルフ・ゼルキンとミエチスワフ・ホルショフスキに師事。17歳でレーヴェントリット賞とフィラデルフィア青年賞を受賞し、フィラデルフィア管弦楽団およびニューヨーク・フィルとの共演を同じ週に行ないステージ・デビュー。1950年、25歳の時には、カザルスが主宰するプラド音楽祭に最年少のアーティストとして出演し、カザルスとの生涯にあわたる友情を確立する(カザルス没後の1975年にはカザルス未亡人のマルタと結婚)。1955年にはスターン、ローズとのピアノ・トリオを結成。1988年には、自分自身のピアノを格納できる特注のトラックとともに4カ月にわたる北米30都市でソロ・リサイタル・ツアーを敢行し、大きな話題となった。(SONY)
【収録情報】
Disc1
● J.S.バッハ:ピアノ協奏曲第1番ニ短調 BWV.1052
アドルフ・ブッシュ(指揮)ブッシュ・チェンバー・プレイヤーズ
録音:1945年4~5月
● J.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲第5番ニ長調 BWV.1050
ヨゼフ・シゲティ(ヴァイオリン)
ジョン・ウンマー(フルート)
パブロ・カザルス(指揮)プラド祝祭管弦楽団
録音:1950年6月
● J.S.バッハ:トッカータとフーガ ホ短調
録音:1950年7月
● モーツァルト:ピアノ協奏曲第14番変ホ長調 K.449
パブロ・カザルス(指揮)ペルピニャン音楽祭管弦楽団
録音:1951年7月
Disc2-3
● ショパン:夜想曲全集(全19曲)
録音:1955年1、2、9月
Disc4
● ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番ハ短調 Op.18
ユージン・オーマンディ(指揮)フィラデルフィア管弦楽団
録音:1956年4月
Disc5
● ブラームス:3つの間奏曲 Op.117
録音:1957年9月
● ブラームス:ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ 変ロ長調
録音:1951年3月
Disc6
● ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番変ホ長調 Op.73『皇帝』
ユージン・オーマンディ(指揮)フィラデルフィア管弦楽団
録音:1958年1月
Disc7
● チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番変ロ短調 Op.23
ユージン・オーマンディ(指揮)フィラデルフィア管弦楽団
録音:1959年4月
Disc8
● ショパン:ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 Op.21
ユージン・オーマンディ(指揮)フィラデルフィア管弦楽団
録音:1959年11月
● シューマン:ピアノ協奏曲イ短調 Op.54
ブルーノ・ワルター(指揮)コロンビア交響楽団
録音:1960年1月
Disc9
● ブラームス:ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 Op.83
ユージン・オーマンディ(指揮)フィラデルフィア管弦楽団
録音:1965年2月
Disc10
● ベートーヴェン:三重協奏曲ハ長調 Op.56
アイザック・スターン(ヴァイオリン)
レナード・ローズ(チェロ)
ユージン・オーマンディ(指揮)フィラデルフィア管弦楽団
録音:1964年4月
● ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番ト長調 Op.58
ユージン・オーマンディ(指揮)フィラデルフィア管弦楽団
録音:1966年12月
Disc11
● シューベルト:ピアノ・ソナタ第17番ニ長調 D.850
録音:1969年6、9月
● ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第21番ハ長調 Op.53
録音:1959年12月(世界初発売)
Disc12(世界初発売)
● ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第24番嬰ヘ長調 Op.78
● ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調 Op.27-2『月光』~第2楽章
録音:1960年4月
● ショパン:夜想曲第5番嬰ヘ長調 Op.15-2
録音:1966年3月、1967年4月
● ショパン:ポロネーズ 変イ長調『英雄』
録音:1967年4月
● ドビュッシー:『亜麻色の髪の乙女』
● ドビュッシー:『月の光』
録音:1968年3月
● メンデルスゾーン:無言歌『5月のそよ風』 Op.62-1
録音:1966年3月、1967年4月
● シューベルト:即興曲 Op.90, D.899~第2番、第3番
録音:1967年4月
● ストラヴィンスキー:ピアノ・ソナタ
録音:1966年3月、1967年4月
ユージン・イストミン(ピアノ)
2015年はこのピアニストの生誕90周年にあたる。2003には物故しているようだが、実はこの人について殆ど知らなかった。わずかにワルターとシューマンのコンチェルトで共演しているくらいというものである。それも評論にはワルターの完全支配下の演奏なんて書かれていた。日本では殆ど話題にならなかったのではなかろうか。いや、おまえが知らないだけと言われるかもしれない。
上のような経歴を読むとたいへんな逸材だったのである。そしてこの人も親世代がロシアからの移民だったというのも同世代のアメリカの音楽家にはありがちなことでもあった。どちらかというとトリオでの活動が主だったみたいなところはある。録音は1945年から68年にかけてであり、モノラル録音が半分、ステレオ録音が半分という構成。ことに初期の若い頃の作品が含まれているのが特徴。協奏曲の場合は初期のものはアドルフ・ブッシュやパブロ・カザロスとの共演もあるが、コロムビア専属らしく、オーマンディ&フィラデルフィアとの共演が多い。また件のワルターとのシューマンの協奏曲も入っている。バラエティに富んだ内容で普段あまりピアノ曲を聴かぬ身でも興味を感じた。ワルターやオーマンディとの共演盤は他にはあまりないので、オーケストラや指揮者の追いかけの貴重な資料にもなる。
↧
December 16, 2015, 3:21 am
ジョセフ・フォン・スタインバーグ監督が「アナタハン」というキワモノ映画を作ったが、これはそのパロディのような作品。川島雄三監督で森繁久弥やフンランキー堺が主演しているので、多分面白いかと期待したが、それは見事に裏切られた感じだ。 何故かギャグもうわすべりで、少しも笑えない。平板なまま、1時間40分余が過ぎるという結果になってしまった。
↧
↧
December 17, 2015, 6:53 pm
![]()
【収録曲】 *世界初音源化 ◎初CD化
●Disc1~2 山田耕筰のオペラ《黒船》自作自演、そして山田の愛弟子、牧野由多可の最初のオペラ
・山田耕筰:交響曲「明治頌歌」森正指揮 東京交響楽団
・山田耕筰:歌劇《黒船》より(ラジオ放送用ナレーション解説付)山田耕筰指揮 東京交響楽団
・牧野由多可:ラジオのためのオペラ《あやめ》(原作:三島由紀夫) 石丸寛指揮 東京室内管弦楽団 *
●Disc3 TBSの芸術祭参加作品として、上田仁と東京交響楽団の初演した3つの交響曲
・林光:交響曲 ト調 上田仁指揮 東京交響楽団
・安部幸明:交響曲第2番 上田仁指揮 東京交響楽団 *
・石桁眞禮生:ハと嬰ヘを基音とする交響曲 上田仁指揮 東京交響楽団 *
●Disc4 大木正夫の「原爆音楽」と、その妻、大木英子の民族的ピアノ協奏曲
・大木正夫:交響的幻想「原爆の図に寄せて」 上田仁指揮 東京交響楽団 *
・大木正夫:「古典彫像に寄する6つの前奏曲と終曲」から5曲 森正指揮 東京交響楽団 *
・大木英子:ピアノと管弦楽のための協奏詩曲「舞い楽」
山田夏精(のちの一雄)指揮 東京交響楽団 金井裕(pf)◎
●Disc5 忘れられた「中間音楽」の旗手、塚原晢夫の音楽
・塚原晢夫:交響曲第1番 山田和男(のちの一雄)指揮 東京交響楽団 *
・塚原晢夫:ピアノ協奏曲 山田和男指揮(のちの一雄) 新室内協会 奥村洋子(Pf) *
・塚原晢夫:交響絵巻《くもの糸》 塚原晢夫指揮 東京交響楽団 *
●Disc6 伊福部昭と間宮芳生の、共に北海道を舞台にした「ラジオのための音楽劇」
・伊福部昭:音楽劇《ヌタック・カムシュペ》 東京室内管弦楽団 劇団七曜会 *
・伊福部昭:「ウポポ」(北海道放送ジングル) *
・間宮芳生:オラトリオ《鴉(からす)》
山田夏精(のちの一雄)指揮 東京交響楽団 出演:中村勘右ェ門 久米明 *
●Disc7 「TBS賞」の軌跡
・大木英子:交響三撰「古今抄」 上田仁指揮 東京交響楽団 *
・土肥泰:「梵唱変容」 上田仁指揮 東京交響楽団 ◎
・杉浦正嘉:「唱礼による交響管弦楽のための音楽」 秋山和慶指揮 東京交響楽団 *
・堀悦子:「半跏思惟」 秋山和慶指揮 東京交響楽団 *
●Disc8 湯山昭のシンフォニーと黛敏郎音楽のラジオ・ドラマ
・湯山昭:10人の奏者のためのセレナーデ 石丸寛指揮*
・湯山昭:子供のための交響組曲 湯山昭指揮 新室内楽協会
・ラジオドラマ《戦争と平和》(音楽:黛敏郎) 武田泰淳原作 *
日本の作曲家たちの足跡を辿るのに貴重な資料がCDとなった。1950年代から60年代に録音されたもので、主にラジオのためのもののようだ。TBSの倉庫から出てきたもののようである。音楽というよりはラジオ劇に近いものもあり、今はない名優の声も入っている。全てモノラルである。
資料としては貴重だが、鑑賞するにはつまらなくなったものもある。たとえば、山田耕筰が自ら振った歌劇「黒船」だ。カットされ、アナウンサーによる語りにおきかえられていたりして、作品そのものが台無しになったようなものも残念ながらある。
↧
December 20, 2015, 4:15 am
演奏
ゲルト・アルブレヒト指揮 ハンブルク国立フィルハーモニー管弦楽団
ドイツCPOから出たペッテションの交響曲シリーズの一つ。いろいろな評を読むとこの作品は比較的聴きやすいということであるが、叙情的な部分が他の作品よりもあるからかもしれない。だが、実際は何かのたうちまわるような感じで救いがない絶望的な音で彩られている。
この作曲家は1911年に生まれたスウェーデンの人で、不幸の連続だったという。それを逆手にとって自分の心情を音楽にぶつけたみたいだ。1911年生まれといえばイタリアのニーノ・ロータと同い年で、現代作曲家の範疇には入る。しかし、前衛的なところはまるでなく、どちらかというと伝統的な書法による作品ばかりのように思う。交響曲の殆どは大編成のオーケストラを要する。低音楽器がずしりと重い響きを鳴らすから、何か深刻なものを突き付けられたような感じになるのである。これも単楽章で45分の時間を要するが、休みなしだから余計にしんどく感じる。
↧
December 27, 2015, 6:15 am
収録情報】
ヴィアンナ・ダ・モッタ:
● 交響曲『祖国』 Op.13 (1895)
第1楽章:Allegro eroico
第2楽章:Adagio molto
第3楽章:Vivace
第4楽章:退廃-戦い-復活
● 序曲『ドナ・イネス・デ・カストロ』 (1886)
● ポルトガルの情景 Op.15~第3番『デュロのチュラ』(F.デ.フレイタスによる管弦楽編)
● 3つの即興曲 Op.18~第2番アレグレット(管弦楽版)
● ビート Op.11(カッスートによる改訂版)
アルヴァーロ・カッスート指揮 ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団
ポルトガルの海外領土(当時)であったサントメ島に生まれたヴィアンナ・ダ・モッタは、幼い頃から音楽の才能を発揮し、1875年から1881年までリスボン国立音楽院でピアノと作曲を学びます。その後、1882年にベルリンに留学しシャルヴェンカ兄弟に師事し、1885年からヴァイマールにてフランツ・リストの高弟となります。リストの死後はハンス・フォン・ビューローにも学び、当時の最も著名なピアニストの一人として名声を獲得しました。作曲家としても、ポルトガル音楽界に最初にナショナリズムの作風を取り入れた先駆者として賞賛されましたが、1900年代になって音楽が現代的な様相を帯びてくると、自らの作風との不一致を感じたのか、1910年頃には作曲活動を停止してしまいます。
しかしながらこのアルバムに収録されている『祖国』を始めとした管弦楽作品は、最近になって人気が高まる傾向にあり、見事なコントラストと重厚な響きからは、まるでリストの交響詩や、一連のワーグナー作品を聴いているような高揚感をも感じさせることでしょう。(NAXOS)
少し珍しいポルトガルの作曲家の作品。ヴィアンナ・ダ・モッタという作曲家は初めて知った。1868年に生まれたこの作曲家は、リストに学び作風もリストの交響詩の響きに似ている。小品はどこかラテン的な感じなところもあるが、後期ロマン派の音楽の作品だなと思った。当然、冒険なのだが演奏のオーケストラがRLPOだから、聴いてみようと思った。このオケはグローヴズの指揮のディーリアスで馴染んだ団体。柔らかくいい音で演奏してくれると期待したからだ。その期待は裏切られることなく、満足のいくものだった。まあしかし、これ以上この作曲家へは深入りしないであろうとも思った。
↧
December 27, 2015, 6:25 am
収録情報】
ティオムキン:
1. 『シラノ・ド・ベルジュラック」(1951) ~序曲
2. 組曲『アラモ』 (1960)
3. 『老人と海』 (1958) ~メイン・テーマ、クバーナ&フィナーレ
4. 『4枚のポスター』 (1952) ~序曲
5. 組曲『ジャイアンツ』 (1956)
6. 『ローマ帝国の滅亡』 (1964) 愛の翳り(インストゥルメンタル・テーマ)
7. 『真昼の決闘』 (1952) ~主題歌「Do Not Forsake Me, Oh My Darlin'」
8. 『ローハイド』 (1959) ~テーマ
9. 組曲『紅の翼』 (1954)
10. ヒッチコック組曲:『ダイヤルMを廻せ!』 (1954) &『見知らぬ乗客』 (1951)
11. 『野性の息吹』(1958) ~主題歌
12. 『サンダウナーズ』 (1960) ~テーマ
13. 『サーカスの世界』 (1964) ~ジョン・「デューク」・ウェインのマーチ
14. 『ピラミッド』 (1955) ~主題歌&ファラオの行進
15. 『友情ある説得』 (1956) ~フェア
16. 『友情ある説得』~主題歌「Thee I Love」
リチャード・カウフマン指揮 ロンドン交響楽団 ロンドン・ヴォイセズ
ハリウッド映画に多くの音楽を提供したディミトリ・ティオムキンの作品集。これを「スター・ウォーズ」などのサウンド・トラックの演奏でも有名なLSOが演奏して収録したもの。中には「真昼の決闘」の主題歌ようにオリジナルよりはうまく歌っているものの、うまくまとめすぎてちょっと違うというものも中にはある。しかし、声楽のないものはフル・オーケストラだから、たいへん聴き応えがある。
↧
↧
December 30, 2015, 11:01 pm
ペッテション:交響曲第8番
トーマス・ザンデルリング指揮 ベルリン放送交響楽団
1984.4.30 ゼンデザール、ベルリン(ライヴ)
CPOのペッテションの交響曲シリーズの一つ。これは当時東ドイツで行われた演奏会ライヴとの表示がある。指揮者はあの巨匠の息子にあたる人で、シベリアで生まれたドイツの指揮者である。
さて、本作品はこの人の交響曲の中で最高の作と言われている。相変わらず暗い音楽だが、第9番や第15番などに比べたら、救いがないような感じでもない。まだ抒情的な部分もあって、聴きやすい。声楽もなく至極オーソドックスでロマン派後期の音楽という聴きざわりである。
↧
January 7, 2016, 11:05 pm
[DISC 1]
《陽旋法に拠る交響曲》(1961)上田仁(指揮)東京交響楽団
(※ 音源提供:TBSヴィンテージクラシックス)
《ピアノ・ソナタ》(1968/1973)村上弦一郎(ピアノ)
《チェロ・ソナタ》(1973)井上頼豊(チェロ)村上弦一郎(ピアノ)
《青春賦》(1974)堀田康夫(指揮)成蹊大学ギターソサエティー
[DISC 2]
バレエ音楽《角兵衛獅子》(1963)福田一雄(指揮)シアターオーケストラトーキョー
この人も映画館で知った作曲家である。「陸軍中野学校」といった増村保造監督の大映作品やテレビ映画「ザ・ガードマン」の音楽を担当した人。やはり伊福部昭の門下生の一人で、同門の小杉太一郎はこの人の妹と結婚しているので、義兄弟という関係。また長兄は新劇俳優の山内明、次兄は脚本家の山内久である。写真を見るとやはり俳優の山内明によく似ている。
さて、やはり作曲家として映画のための音楽ばかりを手がけていたのはではなく、コンサートやバレエのための音楽もしっかり書いている。これはそうした作品を集めた初めてのアルバムとなる。ことに最後のバレエ音楽「角兵衛獅子」は魅力的な作品だった。日本的なメロディやリズムの面白さもあった。演奏はK-カンパニーなどで知られるオーケストラで、蘇演された折の演奏のようである。小難しい現代音楽ばかりという聴衆の思い込みもあって、演奏され聴かれる機会はまだまだ少ない。もったいないようにも思う。
↧
January 10, 2016, 6:04 am
【曲目】
①六つの管楽器の為のコンチェルト (1952)
吉岡アカリ(フルート)、小林裕(オーボエ)、万行千秋(クラリネット)、チェ・ヨンジン(ファゴット)、森博文(ホルン)、
辻本憲一(トランペット)
②弦楽三重奏の為の二つのレジェンド (1952)
高木和弘(ヴァイオリン)、成田寛(ヴィオラ)、江口心一(チェロ)
③舞踊曲「トルソー」 (1955)
村松珠美(ピアノ)、猿田泰寛(ピアノ)
④舞踊組曲「戰國時代」 (1968)
小杉太一郎(指揮) 東京交響楽団 1968年10月6日 石巻市市民会館(ライヴ)
⑤双輪 (1975)
山田節子(箏)、曽我部壽子(箏)
この人も伊福部昭の門下生である。師匠同様に多くの日本映画の音楽担当して活躍した人だが、ここでは映画のためではない作品を収めたもの。殆どがアンサンブルのためのものだが、④のみがオーケストラ作品だ。残念ことに、これだけがモノラル録音で他がデジタル録音なので、古さが目立ってしまっている。そして、驚くことに東映の「宮本武蔵」のテーマ曲と同一の素材が転用されているが、これは作曲家の意図的なものという。確かにあの映画は戦国時代末期から描かれているので、その雰囲気をみごとに表現した音楽でうってつけの素材と感心した。
なお、この人の父君は戦前の日活多摩川の名作に数多く出演した小杉勇である。戦後も俳優の他、監督もこなした人。その多くを息子に音楽を担当させたようである。
↧