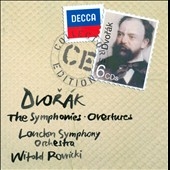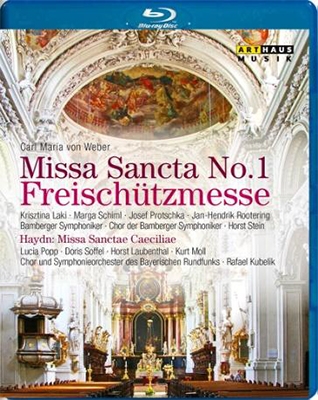
【曲目】
ウェーバー:魔弾の射手ミサ/ハイドン:聖チェチーリア・ミサ
(1)ウェーバー:聖なるミサ 第1番 変ホ長調「魔弾の射手ミサ」
(2)ハイドン:聖チェチーリアのミサ
【演奏】
(1)クリスティアーナ・ラキ(ソプラノ)
マルガ・シュキームル(アルト)
ヨゼフ・プロチュカ(テノール)
ヤン=ヘンドリック・ローテリング(バス)
バンベルク交響楽団・合唱団
ホルスト・シュタイン(指揮)
(2)ルチア・ポップ(ソプラノ)
ドリス・ゾッフェル(アルト)
ホルスト・ラウベンタール(テノール)
クルト・モル(バス)
バイエルン放送交響楽団・合唱団
ラファエル・クーベリック(指揮)
【収録】
(1)1986年 ヴァルトザッセン大聖堂 ライヴ収録, (2)1982年 オットーボイレン大聖堂 ライヴ収録
ウェーバー:魔弾の射手ミサ/ハイドン:聖チェチーリア・ミサ
(1)ウェーバー:聖なるミサ 第1番 変ホ長調「魔弾の射手ミサ」
(2)ハイドン:聖チェチーリアのミサ
【演奏】
(1)クリスティアーナ・ラキ(ソプラノ)
マルガ・シュキームル(アルト)
ヨゼフ・プロチュカ(テノール)
ヤン=ヘンドリック・ローテリング(バス)
バンベルク交響楽団・合唱団
ホルスト・シュタイン(指揮)
(2)ルチア・ポップ(ソプラノ)
ドリス・ゾッフェル(アルト)
ホルスト・ラウベンタール(テノール)
クルト・モル(バス)
バイエルン放送交響楽団・合唱団
ラファエル・クーベリック(指揮)
【収録】
(1)1986年 ヴァルトザッセン大聖堂 ライヴ収録, (2)1982年 オットーボイレン大聖堂 ライヴ収録
どちらも教会の聖堂での演奏である。普通のコンサートではなく、式典に組み込まれたものなのか、観客もおとなしい。ハイドンのソロを務めたルチア・ポップは逝去する11年前の姿で、クライバーの「ばらの騎士」あたりで観たようなふっくらした様子とはことなり、ややほっそりとしたふうに見える。扮装しているのを割り引かないといけないとは思う。
どちらも円熟した指揮者による演奏なので、安心して聴ける。殊にウェーバーの方は珍しい演目で、ホルスト・シュタインによるこの演奏は素晴らしい蘇演との評価は高いという。副題のオペラの題名はあるも、全く関係の作品。作曲者の名前から、知名度を広げようと誰かが付けたものという。1818年にドレスデンで作曲者自身の指揮で初演されたらしいが、このBDに出会うまでは全く知らなかった作品である。





 これはアメリカのCIAが資金を拠出して製作された映画という。東宝が製作して1952年の4月に公開されたが、最近まで現存しないとされた幻の作品だった。戦後作品でもこのような体たらくだ。ところが米国の公文書館から、タイ向けに字幕が施されたプリントが発見されて、自主上映の形でリバイバルされたものだ。
これはアメリカのCIAが資金を拠出して製作された映画という。東宝が製作して1952年の4月に公開されたが、最近まで現存しないとされた幻の作品だった。戦後作品でもこのような体たらくだ。ところが米国の公文書館から、タイ向けに字幕が施されたプリントが発見されて、自主上映の形でリバイバルされたものだ。

![決戦攻撃命令 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51FobogLVPL.jpg)