↧
訃報:ラウラ・アントネッリ
↧
吸血鬼ゴケミドロ(佐藤肇・松竹1968年)
この映画はその公開当時、薄気味悪いという印象で観ようとはしなかった思い出がある。大阪・道頓堀にあった松竹の封切り館にこの映画の宣伝用看板やスティル写真などが飾ってあった。最初に吸血鬼に化す男の異様な風貌が更に怖いと子供心に感じたものだ。ところが、その当時この作品を観た同級生の友人から、宇宙からの侵略者の話で、ホラーというよりSFといった趣だよと聞かされて、拍子抜けしたものだった。
後で知ったのだが、最初に額が割れて人の血を吸うのは、元来が暗殺者で日本で外国大使を暗殺したというもので、悪人なのであった。それに扮していた高英男は俳優ではなく、有名な歌手でシャンソンでは有名な人だった。しかし、出会いが出会いだけに後でテレビでリサイタルをやっていた時に血を吸うんじゃないかと思ったものだ。
物語はかなり警告めいたものを含んだもので、悲劇的な内容である。めでたし、めでたしといった結末ではないところが特徴だ。海外でも公開されて、影響を及ぼしているという。クィンティン・タrンティーノ監督はその代表格で「キル・ビル」に出てくる真っ赤な空は本作へのオマージュだというし、この映画の大ファンということだ。
↧
↧
歌劇『売られた花嫁』全曲(映像~スタジオ収録)

ガブリエラ・ベニャチコヴァー(Sマジェンカ)
ペテル・ドヴォルスキー(Tイエニーク)
インドジフ・インドラーク(Brマジェンカの父)
マリエ・ヴェセラー(Sマジェンカの母)
ヤロスラフ・ホラーチェク(Bsミーハ)
マリエ・ムラゾヴァー(Msハータ)
ミロスラフ・コップ(Tイェニーク)、ほか
プラハ国立歌劇場合唱団
プラハ・フィルハーモニー合唱団
チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
ズデニェク・コシュラー(指)
映像監督:フランティシェク・フリップ
収録:1980年12月-1981年2月
ペテル・ドヴォルスキー(Tイエニーク)
インドジフ・インドラーク(Brマジェンカの父)
マリエ・ヴェセラー(Sマジェンカの母)
ヤロスラフ・ホラーチェク(Bsミーハ)
マリエ・ムラゾヴァー(Msハータ)
ミロスラフ・コップ(Tイェニーク)、ほか
プラハ国立歌劇場合唱団
プラハ・フィルハーモニー合唱団
チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
ズデニェク・コシュラー(指)
映像監督:フランティシェク・フリップ
収録:1980年12月-1981年2月
>チェコの国民的オペラといえばこのスメタナの『売られた花嫁』。物騒な題名と裏腹に、農村を舞台にしたほのぼのとした物語はとても楽しいものです。チェコだけでなくドイツでも上演の盛んなオペラですが、映像は稀。ここに収録されているのは、1981年制作のテレビ映画。ライヴではなく、スタジオで収録されたもの。地元制作だけに、舞台のローカル色は完璧です。さらに、ベニャチコヴァーとドヴォルスキーという、当時のチェコを代表する二大スター共演という豪華な配役。指揮は、チェコの知性派、コシュラー。さすがの出来栄えです。(発売元コメント)
これはLDで出ていたような記憶はあるものの、DVDは輸入物で発売されている模様だ。上記コメントがあるように、映像ソフトは他にドイツ語歌唱によるウィーン国立歌劇場の映像ライヴがあるくらいであろう。そちらはややローカル色はないものだが、こちらは本家本元でオリジナル言語によるものだ。ただ、もっと欲を言えば、ライヴであったらと思う。テレビスタジオで所作を収録し、音は別テイクなのであろう。序曲の部分は指揮者とオーケストラが普通のコンサートをよるような配列で映し出される。時折実景を交えて、やがて幕があがってしまうと、スタジオでドラマが進行するという具合だ。
30年以上も前の映像なので、発色も今一つで経年劣化が認められる。しかし、肝心の音楽はしっかりとした質で鑑賞できるので、安心できる。この作品は1965年のNHKスラブ歌劇で上演された演目で、その映像が存在するのであれば、出して欲しいと思う。
↧
レコード会社の名前がついたオーケストラ
子供の頃、レコード会社の名前のオーケストラは、その会社専属の団体でスタジオ・ミュージシャンを抱えているとばかり思っていた。事実、流行歌などはそうした形態はあったようだ。たとえば「ビクター・オーケストラ」とか「コロムビアオーケストラ」といった類だ。
しかし、これがクラシックになると、海外の事情になるので、少し変わってくる。上京して大学に入ってから、その辺りの事情に詳しい仲間がいて、ブルーノ・ワルターが指揮している「コロムビア交響楽団は西と東と別にある」というようなことを教唆されて、ヘ~と言って目を丸くしたものである。その後、レコードにクレジットされている「コロムビア交響楽団」「RCAビクター交響楽団」「キャピトル交響楽団」とはどういうことか、関心を持ちだした。
件のワルター盤以外にも「コロムビア交響楽団」を指揮した人は数人いる。その内、イーゴリ・ストラヴィンスキーが自作を録音するのに使用した団体はワルターの専属のものと同一らしい。しかし、他の人やワルターでも一部のものは西海岸の団体ではないことがあることが理解できるようになった。アメリカは契約社会なので、本当の名前を出せないことがあったり、寄せ集めのピックアップだったりする場合の方便だということだ。それは「RCAビクター交響楽団」なども同じことであることも。
それからレコード会社はオケの名称を変えたりもする。たとえば戦前RCA専属だったフィラデルフィア管弦楽団は「フィラデルフィア交響楽団」と記されていたり、ウィーン・フィルが「ダニューブ交響楽団」、LSOが「テームズ交響楽団」といった具合にやりたい放題の例もある。専属の関係もあるだろうが、一種の営業戦略もあったのかもしれない。専属の関係で本当の名前が出せない場合、適当に名称変更した事例はデッカ系の会社がNYPを起用して、録音した折に「ニューヨーク・シタジアム交響楽団」という名称を使っている。当時はCBS専属なので、本名を名乗れない方便である。こうしてみると音楽というよりは契約とか営業的な作戦だったりの問題で別の意味で興味深いテーマではある。
↧
フランス国立管弦楽団 高音質による、未発表演奏会の80年

【曲目】
STEREO=S MONO=M
[CD1] フランスの伝統 [1h18'16]
・ドビュッシー:夜想曲〔1. 雲 2. 祭 3.シレーヌ(セイレン)〕[5'07]
デジレ=エミール・アンゲルブレシュト(指揮)、RTF 合唱団
録音:1958年3月20日(ドビュッシー没後40周年祭)、シャンゼリゼ劇場 M
・ラロ:「イスの王」序曲 [12'18]
ポール・パレー(指揮)
録音:1970年11月25日、シャンゼリゼ劇場 S
・ルーセル:バッカスとアリアーヌ [16'36]
シャルル・ミュンシュ(指揮)
録音:1966年1月1日、バーデン=バーデン M
・プーランク:村人の歌 [10'51]
ロジェ・デゾルミエール(指揮)、ピエール・ベルナック(バリトン)
録音:1944年4月24日、サル・ガヴォー M
(ピエール・シェーファー実験的スタジオ録音)
・アルベリク・マニャール(1865-1914):
Hymn to justice(正義への賛歌)op.14 [13'13]
マニュエル・ロザンタール(指揮)
録音:1944年9月28日、シャンゼリゼ劇場 M
(1944年パリ解放後、第1回目のコンサートの記録)
[CD2] 1950年代のレパートリーの拡張 [1h17'58]
・ベートーヴェン:序曲コリオラン [7'25]
カール・シューリヒト(指揮)
録音:1959年3月24日、シャンゼリゼ劇場 S
(フランス国立管弦楽団25周年記念演奏会)[ 既出ALT 210/11]
・マーラー:さすらう若人の歌 [16'16]
カール・シューリヒト(指揮)
ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(バリトン)
録音:1957年9月9日、ブザンソン市営劇場 M
[ 既出TAH 646]
・R.シュトラウス:ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら [15'13]
ヨーゼフ・クリップス(指揮)
録音:1957年10月10日、シャンゼリゼ劇場 M
・アルバン・ベルク:ペーター・アルテンベルクの絵はがきの文による5つの管弦楽伴奏歌曲 op.4 [11'35]
ヤッシャ・ホーレンシュタイン(指揮)、イルマ・コラッシ(ソプラノ)
録音:1953年5月4日、シャンゼリゼ劇場 M
・ラヴェル:2つのヘブライの歌
パウル・クレツキ(指揮)、ヴィクトリア・デ・ロス・アンヘレス(ソプラノ)
録音:1955年12月1日、シャンゼリゼ劇場 M
・ストラヴィンスキー:火の鳥(組曲)[19'26]
アンドレ・クリュイタンス(指揮)
録音:1956年1月30日、シャンゼリゼ劇場 M
[CD3] ORTF からONFへ
( フランス国立放送管弦楽団からフランス国立管弦楽団へ) [1h16'54]
・プロコフィエフ:ロミオとジュリエット 組曲第1番&第2番(抜粋)[23'53]
〔組曲第2番より- モンダーギュー家とキャピュレット家、少女ジュリエット、
ジュリエットの墓の前のロメオ/第1組曲より- ティボルトの死〕
セルジュ・チェリビダッケ(指揮)
録音:1974年5月29日、シャンゼリゼ劇場 S
・ラヴェル:シェエラザード [17'59]
レナード・バーンスタイン(指揮)、マリリン・ホーン(ソプラノ)
録音:1975年9月20日、シャンゼリゼ劇場 S
・ストラヴィンスキー:春の祭典 [34'57]
ロリン・マゼール(指揮)
録音:1980年7月8日、シャンゼリゼ劇場 S
[CD4] 旅の仲間~バーンスタイン、小澤征爾、リッカルド・ムーティ [1h2'29]
・アンブロワーズ・トマ:レーモンあるいは王妃の秘密の序曲 [9'26]
レナード・バーンスタイン(指揮)
録音:1981年11月21日、シャンゼリゼ劇場 S・ドビュッシー:海 [23'55]
小澤征爾(指揮)
録音:1984年5月28日、シャンゼリゼ劇場 S
・ケルビーニ:「ロドイスカ」序曲 [10'26]
リッカルド・ムーティ(指揮)
録音:2004年1月15日、シャンゼリゼ劇場 S
・ハイドン:交響曲第39番 ト短調 [18'36]
リッカルド・ムーティ(指揮)
録音:2008年3月13日、シャンゼリゼ劇場 S
[CD5] 20世紀から21世紀へ
~シャルル・デュトワ、クルト・マズア、ダニエレ・ガッティ [1h15'21]
・ベルリオーズ:序曲「海賊」[8'16]
シャルル・デュトワ(指揮)
録音:1993年12月3日、シャンゼリゼ劇場 S
・ショスタコーヴィチ:交響曲第1番 ヘ短調 op.10 [31'41]
クルト・マズア(指揮)
録音:2004年9月23日、シャンゼリゼ劇場 S
・ワーグナー:トリスタンとイゾルデより前奏曲と愛の死 [18'50]
ダニエレ・ガッティ(指揮)
録音:2013年10月30日、パルマ王立劇場 S
・ラヴェル:ダフニスとクロエ 組曲第2番 [16'26]
ダニエレ・ガッティ(指揮)
録音:2012年3月28日、シャンゼリゼ劇場 S
[CD6] 頂上決戦その1 [1h0'54]
・チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35
オイゲン・ヨッフム(指揮)、クリスチャン・フェラス(ヴァイオリン)
録音:1964年4月9日、シャンゼリゼ劇場 M
・プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第3番 ハ長調 op.26
クラウディオ・アバド(指揮)、マルタ・アルゲリッチ(ピアノ)
録音:1969年11月12日、シャンゼリゼ劇場 S
[CD7] 頂上決戦その2 [1h19'07]
・ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77
ユージン・オーマンディ(指揮)、アイザック・スターン(ヴァイオリン)
録音:1972年1月24日、シャンゼリゼ劇場 S
・ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 op.104
シャルル・デュトワ(指揮)、ヨーヨー・マ(チェロ)
録音:1993年1月21日、シャンゼリゼ劇場 S
[CD8] 初演[1h14']
・アンリ・デュティユー:交響曲第1番 [31'21]
ロジェ・デゾルミエール(指揮)
録音:1951年6月7日、シャンゼリゼ劇場(世界初演) M
・プーランク:モンテ・カルロの女 [7'31]
ジョルジュ・プレートル(指揮)
デュニス・デュヴァル(ソプラノ)
録音:1961年12月5日、シャンゼリゼ劇場(世界初演) S
・メシアン:7つの俳諧
小澤征爾(指揮)
イヴォンヌ・ロリオ(ピアノ)
録音:1966年9月15日、ブザンソン市営劇場(放送初演) S
・クセナキス:ST 48 [9'32]
ルーカス・フォス(指揮)
録音:1968年10月26日、テアトル・デュ・ラ・ミュジク・ドゥ・パリ(世界初演) S
・ルチアーノ・ベリオ:カルモ [4'40]
ルチアーノ・ベリオ(指揮)、キャシー・バーベリアン(メゾ・ソプラノ)
録音:1976年5月14日、サル・プレイエル(パリ初演) S
フランス国立管弦楽団は、1934年の設立なのだそうだ。2014年に80周年を迎えて、その記念で主に未発表の録音を集めた8枚組BOXがリリースされたのが、これだ。
レコード会社の専属から外れて、いろいろな組み合わせで指揮者やソリストが登場するのは、興味津々である。同じヴァイオリンでもフェラスとスターンとは音色も異なったりする。演奏者としては比較されるのだから、この種の録音物が出るのは心地良くはないのかもしれない。指揮者もしかり。ただ同一曲の異なる演奏の収録はない。 1枚ことにタイトルがあって、テーマごとに収録という心憎いことをしてくれている。
概ね比較的新しいものが多いという印象だが、1944年の録音とか50年代のものも散見される。モノラル録音でも安定した音のように聴こえる。最後の1枚はこのオーケストラが初演したものを集めたもの。放送局のオケなので現代音楽をやる機会は多いのであろう。
↧
↧
バーンスタイン&METによる「カルメン」

マリリン・ホーン(Ms カルメン)
ジェイムズ・マックラッケン(T ドン・ホセ)
トム・クラウセ(Bs-Br エスカミーリョ)
アドリアーナ・マリポンテ(S ミカエラ)
コレット・ボキー(S フラスキータ)
マルシア・ボールドウィン(Ms メルセデス)
ドナルド・グラム(BS スニガ)、
ラッセル・クリストファー(Br リーリャス・パスティア、ダンカイロ)
アンドレア・ヴェリス(T レメンダード)
マンハッタン・オペラ・コーラス
レナード・バーンスタイン指揮 メトロポリタン歌劇場管弦楽団・児童合唱団
録音時期:1972年9月、10月
録音場所:ニューヨーク、マンハッタン・センター
録音方式:ステレオ(アナログ/セッション)
録音場所:ニューヨーク、マンハッタン・センター
録音方式:ステレオ(アナログ/セッション)
原盤はDGで当時はまだ、バーンスタインはCBSの専属だったので、びっくりした記憶がある。そして、VPOを振ったいくつかのオペラはあるにしても、オペラは珍しいと思ったものだ。ただし、今回ペンタトーンから出たハイブリットSACDで初めて中味を聴いたことになる。ライヴだとばかり思っていたら、セッション録音であるし、METの合唱は児童合唱のみでメインのコーラスは別団体がクレジットされているのも今回気付いたことだった。
まず、冒頭の前奏曲がかなり遅いテンポなのだ。何か弾むような演奏を期待したのだが、見事に裏をかかれたような感じだ。しかし、幕が上がった部分はそう違和感はない。普段共演しているNYPとは肌合いが異なるのか、いくぶん遠慮しているようなところがあるのかもしれない。録音はデジタル収録ではないが、当時としては良い方ではないかと思う。
↧
しなの川(松竹1973年)

この映画は由美かおるの全裸姿のスティル写真が突出して有名だった。バレエで鍛えた肢体を惜しみなく露出したということで話題になったものだ。
原作は劇画であって、やや作り話がすぎる感じがして、必ずしも共感できなかった。いろいろな作品を発表する野村芳太郎監督の作品ということで観たのだが、松本清張ものに見られる鋭さもないような感じである。戦前の型にはまった生活を打破しようとする女性の話ではあることに加えて、同性愛のエピソードもあって、なかなかユニークな話なのだが、全て自分勝手な行動に感じてしまい、それが共感に乏しい原因かもしれない。左翼かぶれの国語の教師役なのは今の東映の社長になっている岡田裕介。ここでもやや演技は一本調子で、なにやっても同じに見えた。
↧
LSOによるレスピーギ:ローマ三部作(エヴェレスト)

【曲目】
レスピーギ:
(1)交響詩「ローマの噴水」
(2)交響詩「ローマの松」
(3)交響詩「ローマの祭り」
【演奏】
サー・マルコム・サージェント(1)(2)、サー・ユージン・グーセンス(3)(指揮)
ロンドン交響楽団
【録音】
1959年10月(1)(2)、1960年8月(3)/ウォルサムストウ・アセンブリー・ホール(ロンドン)
レスピーギ:
(1)交響詩「ローマの噴水」
(2)交響詩「ローマの松」
(3)交響詩「ローマの祭り」
【演奏】
サー・マルコム・サージェント(1)(2)、サー・ユージン・グーセンス(3)(指揮)
ロンドン交響楽団
【録音】
1959年10月(1)(2)、1960年8月(3)/ウォルサムストウ・アセンブリー・ホール(ロンドン)
二人の指揮者がLSOを振ってエヴェレスト・レーベルに入れたレスピーギのローマ三部作。優秀な録音としてオーディオ・ファンの間では有名な録音群ではあるが、この曲目はそうした録音には適したものではある。二人の指揮者は有名な人たちだが、サージェントは癌で比較的早く亡くなってしまったし、グーゼンスはあるスキャンダルが元で表舞台から退く事態に追い込まれてしまっているので、これは彼らの活動の貴重な記録でもある。
今回聴いてみると各楽器の分離も良く、それぞれがはっきりと聴こえる。その代わりアラもわかりやすくなっている点は痛しかゆしといった印象である。聴いたのは通常のCDであるが、SACDで聴くともっと鮮明になっているのかもしれない。
↧
フィレンツェ五月音楽祭の創立者、ヴィットーリオ・グイ

【曲目】
(CD1)
シューベルト:交響曲第8番 ロ短調 D759 「未完成」
シューマン:「マンフレッド」序曲 Op.115
ブラームス:大学祝典序曲 Op.80
ワーグナー:歌劇「タンホイザー」序曲
シューベルト:交響曲第8番 ロ短調 D759 「未完成」
シューマン:「マンフレッド」序曲 Op.115
ブラームス:大学祝典序曲 Op.80
ワーグナー:歌劇「タンホイザー」序曲
ワーグナー:歌劇「さまよえるオランダ人」序曲
(CD2)
ロッシーニ:歌劇「ウィリアム・テル」序曲
ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲
デュカス:魔法使いの弟子
グリンカ:幻想曲「カマリンスカヤ」
ボロディン:歌劇「イーゴリ公」―韃靼人(ポロヴェツ人)の踊り
ムソルグスキー:交響詩「禿山の一夜」
シベリウス:交響詩「フィンランディア」
【演奏】
ヴィットーリオ・グイ(指揮) フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団
ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲
デュカス:魔法使いの弟子
グリンカ:幻想曲「カマリンスカヤ」
ボロディン:歌劇「イーゴリ公」―韃靼人(ポロヴェツ人)の踊り
ムソルグスキー:交響詩「禿山の一夜」
シベリウス:交響詩「フィンランディア」
【演奏】
ヴィットーリオ・グイ(指揮) フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団
この指揮者はいくつかのオペラのライヴ録音を聴いたことはあるが、コンサート・ピースをまとめて聴くのは今般が初めてである。オペラはイタリア・オペラばかりだったが、上の曲目を見るとイタリアものはロッシーニの「ウィリアム・テル」序曲のみというプログラムなのがおもしろい。ヴェルディ、ロッシーニばかりを指揮していたわけではなく、レパートリーは広かったことを示している。
ステレオながら、劣化していてやや不安定な状態なのが残念だが、総じてオーケストラの音は軽く(ピッチが高めに収録されているということもある)、ワーグナーなんかは物足らない感じがした。ただ、曖昧さを排した指揮ぶりはこの人の特徴のようでツボにはまったものは、ワクワクする。意外に後半のボロディンやムソルグスキーは録音状態が惜しいが気に入った。
↧
↧
ストコフスキー&ニューヨーク・フィルの1947&1949年録音集

【収録情報】
1. エネスコ:ルーマニア狂詩曲第1番(録音時期:1947年2月20日)
2. ボロディン/ストコフスキー編:ダッタン人の踊り(録音時期:1949年11月27日)
3. ドビュッシー/ストコフスキー編:沈める寺(録音時期:1947年2月13日)
4. バウアー:サン・スプレンダー Op.19c(録音時期:1947年10月25日 世界初録音)
5. ブリテン:ピアノ協奏曲 Op.13(録音時期:1949年11月27日) ジャックス・アブラム(ピアノ:5)
レオポルド・ストコフスキー指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック
いずれも、カーネギー・ホールでのライヴ録音。CBSが放送用に録ったものかもしれない。少し奥行き感に欠けるが、ひどい状態ではない。演奏は少々粗い感じもする。
さて、このコンビが米コロムビアに録音したものが、以前出ていたし、同時期のマーラーの第8番といった大曲の録音も存在する中、まだこのようなものがあったとは知らなかった。この中で自身がアレンジしたものが2曲、アメリカの女性作曲家バウアーという人の今ではあまり接することのない作品が目玉だと思った。メインはブリテンのピアノ協奏曲ということになるかもしれないが、手に取った主因は2~4の収録があったからだ。
3については既にサヴァリッシュ&フィラデルフィアのデジタル録音があるのだが、スコトフスキー自身が振るというのがポイントだった。古くて、サヴァリッシュ盤ほどきらびやかではないのは仕方がない。割とあっさりと仕上げている感じだった。むしろ、2の方が驚きがあった。通常聴かれない音楽から始まる。そして中間部の男性が勇壮に踊る部分は割愛されている。それでも興奮を呼ぶ演奏だったようで、拍手が凄かった。ブリテンの協奏曲の同じ日なのが注目だった。
↧
いのち・ぼうにふろう(東宝・俳優座1971年作品)
山本周五郎の「深川安楽亭」を仲代達矢の夫人、隆巴が脚色して、小林正樹監督がメガフォンを取った時代劇。原作の題名は密貿易に携わる悪党たちの巣窟である一膳飯屋のことである。
悪党ではあるが、ここに出てくる男たちは人情味が残っていて、若いカップルを助けるために最後の奮闘するという話。山本周五郎の原作だから、どこか人情の機微が描かれている。原作は読んだことはあるものの、かなり前なので、曖昧な記憶の彼方でしかない。
映画はかなり演劇的な匂いの強いものになっている。ほぼ、場所が限られている。出ている連中も俳優座を始め、前進座の御大の中村翫右衛門まで出ている。映画俳優は、名無しの男役の勝新太郎と若い娘役の酒井和歌子くらいである。したがって、映画としてはやや演技に違和感があるのだが、見応えはある。71年の作品にも拘わらずモノクロ作品。殺伐とした雰囲気を盛り上げていると思った。
↧
伊福部昭百年紀Vol.3
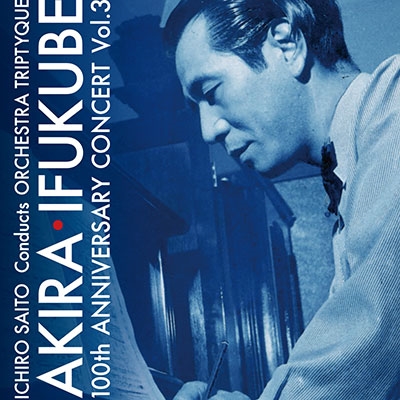
【曲目】
1. HBCテレビ 放送開始と終了のテーマ
2. 北海道讃歌
3-18. 「大怪獣バラン」組曲
第1部 TV版
No.2
No.3
No.2
No.14
第2部 映画版
No.1 「メインタイトル」
No.2 「20世紀の神秘」
No.5 「婆羅陀魏山神」
No.6 「バラン復活」
No.13 「バラン対哨戒艇うらなみ(A)」
No.12 「バラン対迎撃機ネプチューン」
No.16 「特車隊出動」
No.15 「爆雷攻撃開始」
No.14 「バラン対哨戒艇うらなみ(B)」
No.16 「特車隊出動」
No.18 「特殊火薬」
No.20 「エンディング」
19-30. 「ゴジラ」組曲 改訂版
M-1. 「メインタイトル」
M-6. 「大戸島の神楽」
M-9. 「大戸島のテーマ」
M-7. 「嵐の大戸島」
M-11. 「フリゲートマーチ」
M-C. 「ゴジラ東京湾へ」
M-A. 「ゴジラの猛威」
M-B. 「決死の放送」
M-16. 「ゴジラ迎撃せよ」
M-19. 「帝都の惨状」
「平和への祈り」
M-23. 「エンディング」
31-38. 「モスラ対ゴジラ」組曲
No.1 「メインタイトル」
No.4 「巨卵漂着」
No.5 「小美人のテーマ」
No.6 「小美人の回想」
P.S. No.3 「聖なる泉」
No.25 「幼虫モスラ対ゴジラ」
No.18 「モスラの旅立ち」
No.1,2,7 「マハラ・モスラ」
39-53. 「キングコング対ゴジラ」組曲
No.1 「メインタイトル」
No.2 「世界驚異シリーズ」
No.6 「ファロ島」
No.14 「大ダコ対キングコング」
No.18 「埋没作戦準備」
No.20 「100万∨作戦準備」
No.10 「ゴジラの恐怖」
No.27 「キングコング輸送作戦」
No.19 「キングコング対ゴジラ」
P.S. No.4「ふみ子救出作戦I」
No.15「眠れる魔神(前半)」
No.26「ふみ子救出作戦II」
No.12「眠れる魔神(後半)」
No.1 「メインタイトル(リフレイン)」
No.30 「エンディング」
54-55. 「海底軍艦」より
No.3「メインタイトル」
No.20「ムウ帝国の祈り」
56. 「キングコング対ゴジラ」より(アンコール)
【演奏】
作曲:伊福部昭
構成・復元:鹿野草平
指揮:齊藤一郎
コンサートマスター:工藤春彦
演奏:オーケストラ・トリプティーク http://3s-ca.jimdo.com/
合唱:伊福部昭百年紀合唱団
エレクトーン:菊地夕夏
ピアノ:小形さくら、林繭
【録音】
2014年11月24日(すみだトリフォニーホールにてライヴ録音)
1. HBCテレビ 放送開始と終了のテーマ
2. 北海道讃歌
3-18. 「大怪獣バラン」組曲
第1部 TV版
No.2
No.3
No.2
No.14
第2部 映画版
No.1 「メインタイトル」
No.2 「20世紀の神秘」
No.5 「婆羅陀魏山神」
No.6 「バラン復活」
No.13 「バラン対哨戒艇うらなみ(A)」
No.12 「バラン対迎撃機ネプチューン」
No.16 「特車隊出動」
No.15 「爆雷攻撃開始」
No.14 「バラン対哨戒艇うらなみ(B)」
No.16 「特車隊出動」
No.18 「特殊火薬」
No.20 「エンディング」
19-30. 「ゴジラ」組曲 改訂版
M-1. 「メインタイトル」
M-6. 「大戸島の神楽」
M-9. 「大戸島のテーマ」
M-7. 「嵐の大戸島」
M-11. 「フリゲートマーチ」
M-C. 「ゴジラ東京湾へ」
M-A. 「ゴジラの猛威」
M-B. 「決死の放送」
M-16. 「ゴジラ迎撃せよ」
M-19. 「帝都の惨状」
「平和への祈り」
M-23. 「エンディング」
31-38. 「モスラ対ゴジラ」組曲
No.1 「メインタイトル」
No.4 「巨卵漂着」
No.5 「小美人のテーマ」
No.6 「小美人の回想」
P.S. No.3 「聖なる泉」
No.25 「幼虫モスラ対ゴジラ」
No.18 「モスラの旅立ち」
No.1,2,7 「マハラ・モスラ」
39-53. 「キングコング対ゴジラ」組曲
No.1 「メインタイトル」
No.2 「世界驚異シリーズ」
No.6 「ファロ島」
No.14 「大ダコ対キングコング」
No.18 「埋没作戦準備」
No.20 「100万∨作戦準備」
No.10 「ゴジラの恐怖」
No.27 「キングコング輸送作戦」
No.19 「キングコング対ゴジラ」
P.S. No.4「ふみ子救出作戦I」
No.15「眠れる魔神(前半)」
No.26「ふみ子救出作戦II」
No.12「眠れる魔神(後半)」
No.1 「メインタイトル(リフレイン)」
No.30 「エンディング」
54-55. 「海底軍艦」より
No.3「メインタイトル」
No.20「ムウ帝国の祈り」
56. 「キングコング対ゴジラ」より(アンコール)
【演奏】
作曲:伊福部昭
構成・復元:鹿野草平
指揮:齊藤一郎
コンサートマスター:工藤春彦
演奏:オーケストラ・トリプティーク http://3s-ca.jimdo.com/
合唱:伊福部昭百年紀合唱団
エレクトーン:菊地夕夏
ピアノ:小形さくら、林繭
【録音】
2014年11月24日(すみだトリフォニーホールにてライヴ録音)
タイトルからこれが3枚目の伊福部生誕100周年に関するライヴの第3弾である。
今回は怪獣映画のための音楽がメインだが、最初の珍しい音楽が演奏されている。HBCという北海道の放送局のテレビ放送開始と終了の音楽と合唱曲「北海道讃歌」が収録されているのが目を惹く。前者は何かガムラン音楽みたいな感じで南方の民族音楽みたいなのが面白い。後者はこの人独特の合唱と管弦楽のための作品ながら、北海道以外で演奏されるのは、この収録の演奏会が初めてというもの。その後、怪獣ものや特撮ものの音楽が続く。これらは戦前・戦中の作品の転用が多々あって、戦争の記憶が色濃く残っているという印象だ。たとえば「ゴジラ」の「大戸島の神楽」の音楽は「日本狂詩曲」の素材。「ゴジラ」以外に「てんやわんや」という1950年の松竹作品のタイトルバックにも使われている。「大怪獣バラン」でも「兵士の序奏」の素材が出てくるし、ゴジラのテーマ自体が1948年の「ヴァイオリンと管弦楽のための協奏的狂詩曲」からの転用だ。「ゴジラ」のフリゲートマーチも戦時中の吹奏楽作品「古志舞」が基になっている。「ゴジラ」の3年前の作品「源氏物語」で主人公たちが馬で疾走するシーンに既に転用されている素材でもある。
ただ惜しむらくは合唱の規模が小さく、歌詞がよく聞き取れない。「ゴジラ」の祈りの音楽でも映画のサウンドトラックの方がまだ合唱が鮮明だったように感じた。オーケストラや合唱もこの企画に合わせた臨時編成なのかもしれない。
↧
私の履歴書:浅丘ルリ子

2015年7月の日本経済新聞の「私は履歴書」は女優の浅丘ルリ子である。デビュー前後のことや、監督や他の俳優とのかかわり、それに出演作のことなどが触れられていて、日本映画のファンにとってはちょっとした資料になる。
以前にも高橋英樹が礼儀にはうるさい先輩と語っていたが、その一端も書かれている。殊に撮影の集合時間に遅刻するのを許さない姿勢で厳しい。それは石原裕次郎や勝新太郎のような大スターでも同じというのが小気味よい。いわば「時間泥棒」の行為だからだと思う。まだ進行中なので、これを書いた段階では石坂浩二との出会いまでである。
↧
↧
BPOワルトビューネ2015
<曲 目>
1.20世紀フォックス・ファンファーレ(アルフレッド・ニューマン)
2.映画「戦艦バウンティ」から 序曲(ブロニスラウ・ケイパー)
3.映画「ローラ殺人事件」 テーマ曲「ローラ」(デーヴィッド・ラクシン)
4.ピアノ協奏曲 イ短調 作品16(グリーグ)
5.映画「大いなる西部」 テーマ曲(ジェローム・モロス)
6.映画「ロビン・フッドの冒険」から シンフォニック・ポートレイト(コルンゴルト)
7.映画「トムとジェリー」(スコット・ブラッドリー)
8.映画「ベン・ハー」組曲から 序曲 戦車の行進(ミクロス・ロージャ)
9.映画「インディ・ジョーンズ レイダース/失われたアーク」から レイダース・マーチ(ジョン・ウィリアムズ)
10.映画「E.T.」から フライング・テーマ(ジョン・ウィリアムズ)
11.映画「スター・ウォーズ」 メイン・タイトル(ジョン・ウィリアムズ)
12.ベルリンの風(パウル・リンケ)
<出 演>
ピアノ: ラン・ラン
<管弦楽>ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
<指 揮>サイモン・ラトル
収録: 2015年6月28日 ワルトビューネ野外音楽堂(ベルリン)
1.20世紀フォックス・ファンファーレ(アルフレッド・ニューマン)
2.映画「戦艦バウンティ」から 序曲(ブロニスラウ・ケイパー)
3.映画「ローラ殺人事件」 テーマ曲「ローラ」(デーヴィッド・ラクシン)
4.ピアノ協奏曲 イ短調 作品16(グリーグ)
5.映画「大いなる西部」 テーマ曲(ジェローム・モロス)
6.映画「ロビン・フッドの冒険」から シンフォニック・ポートレイト(コルンゴルト)
7.映画「トムとジェリー」(スコット・ブラッドリー)
8.映画「ベン・ハー」組曲から 序曲 戦車の行進(ミクロス・ロージャ)
9.映画「インディ・ジョーンズ レイダース/失われたアーク」から レイダース・マーチ(ジョン・ウィリアムズ)
10.映画「E.T.」から フライング・テーマ(ジョン・ウィリアムズ)
11.映画「スター・ウォーズ」 メイン・タイトル(ジョン・ウィリアムズ)
12.ベルリンの風(パウル・リンケ)
<出 演>
ピアノ: ラン・ラン
<管弦楽>ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
<指 揮>サイモン・ラトル
収録: 2015年6月28日 ワルトビューネ野外音楽堂(ベルリン)
深夜のワルトビューネ2015を鑑賞。もちろんBDに録画したものを鑑賞している。今回はグリーグのピアノ協奏曲以外は全て映画関連のものだ。最後の「ベルリンの風」はいつもアンコール的に流れるから除外しての話。
ベルリン・フィルにとっては、難しいものではないだろうが、極めて珍しい取り組みかと思う。しかもその殆どはハリウッド発のもの。コルンゴルドなどがナチの手を逃れてアメリカに渡り、映画音楽に携わって、フルオーケストラ編成用にして、提供するようになったその成果群といっていい。ロビンフッドの音楽の時はその衣裳を着た打楽器奏者なんかがいて、茶目ッ気なえんしゅつもあったりする。「トムとジェリー」の音楽だけは編成を小さくして3本のサクソフォンが入り、トランペットもピストン楽器に持ち替えての演奏で、ジャズ風のアレンジなのが面白い。テーマだけでなく、劇中の音楽も編集されている。
↧
特急三百哩(三枝源次郎・日活大将軍1928年)
CSの衛星劇場で放映されたので、知った映画。解説の大林宣彦監督も企画に上がるまで、存在を知らなかったと語っている。日活には保管されておらず、九州の旧国鉄関係のところに保管されていた。しかもほぼ完全な状態である。残念ながら、この当時の作品はあってもどこかが欠けていたりするものだが、本作は例外なのだろう。鉄道関係者が記録用に保管していたのだろう。その辺の経緯は太田米男氏という映画保存にも詳しい大学の先生が、レポートをまとめておられる。こういう映画もまた監督の三枝源次郎という人も知らなかった。三枝監督は溝口健二監督はほぼ同世代で2つ若い。没年不詳となっている。前半はサイレント作品を手掛けていたが、朝日新聞の記録映画のセクションに入って、ドキュメンタリーを制作していたようだ。
映画自体もたいへん貴重だが、そこに出てくる鉄道の様子もたいへん貴重である。C51、C53、9600、8620型だけでなく8900型といった昭和初期にはきえていった機関車もまだ現役で走っている姿が認められる。1928年2月公開ということは撮影は1927年頃から始まっていたのではなかろうか。1925年に螺旋式連結器から自動連結器に一斉変更になって、まだ2~3年の頃。螺旋式で使われていた緩衝器の跡が車両に残っているのが散見される。話は九州が舞台のようだが、出てくるのは梅小路機関区であり、走行路線も京都近辺のようである。
出演は島耕二が主演で、滝花久子や山本嘉一らが助演している。島耕二は後年監督として活躍した人だが、1930年代前半までは、日活の現代劇のスターだった。「情熱の詩人・石川啄木」とか「裸の街」といった作品に主演している。これらの作品は残っているかどうか、わからないが、名作ということで文献的には名が残っている。滝花久子は田坂具隆監督の夫人になった人だが、老年になっても脇役で活躍、品のいい老婆になって映画やテレビにも出ていた。ここではヒロインを演じたスターである。山本嘉一は鉄道省長官役で登場し、貫録十分。1939年には亡くなっているのだが、内田吐夢監督の「土」の頑固な舅役や阪東妻三郎が大石内蔵助になった日活の「忠臣蔵」で吉良なんかをやっていた。そうした名の知れた人も出演、それなりに力の入った作品のように見受ける。
保存していたところ、修復してくれた人に将に感謝である。
↧
兵隊やくざ大脱走(田中徳三・大映京都1966年)

「陸軍中野学校」と同様に増村保造監督が最初に手掛けて、東京の撮影所に開始された後に、シリーズ化となって、撮影所も京都に移ったのが本シリーズ。これは後期の作品である。本シリーズは敗戦直前の満州という設定で、ソ連軍の侵攻やゲリラに振り回される日本軍の姿が背景にある。二人の主人公ともに我が道を行くというところが痛快で、人気シリーズになったもの。
「陸軍中野学校」もだったが、第1作はどこか戦争の空しさみたいなものが濃い感じだったが、回を重ねるに連れてアクション娯楽の要素が強くなっていった。これもそうしたプログラム・ピクチュアに組み込まれた作品と言ったらそれまでだが、組織の枠組みを超えようとする二人の兵隊の行動に日頃の鬱憤を観客は喝采していたのかもしれない。開拓避難民を助けるという後半の山場だが、軍隊本体は民間人保護には否定的であることがさらりと出てくる。
↧
濡れた逢いびき(前田陽一・松竹1967年)
前田陽一監督の初期の作品。土屋隆夫の原作を野村芳太郎と吉田剛がシナリオにして撮っている。喜劇のようであり、サスペンスのようであり、ちょっと微妙なテーストの作品である。
とある村の郵便局の局長の姪とその局の臨時雇いの青年のチグハグな関係を描いたもの。女の方は村の秀才ではあるが女たらしの青年に騙されて自殺しようとしているし、青年の方は仕事を適当にやる冴えない奴である。女は毒薬を持っていて、ドン・ファンのような青年に復讐を果たし、二人は利害関係を一にして深い関係になるが、互いに紹介された相手の方が気に入ってしまい、お互いに殺意を持ってしまうというのが粗筋。
共演は谷幹一や柳沢真一、三遊亭歌奴など助演しているので、全体的にコミカルな雰囲気。ヒロインの加賀まりこは相変わらず小悪魔的でそれなりの雰囲気を出しているが、青年役の田辺昭知は素人芝居の域を出ない。当時のGSの人気にあやかってザ・スパイダースのリーダーとしてまたドラマーとして活躍してきた人だが、同じメンバーの堺正章などの影にかくれてあまり、パフォーマンスをしない人だった。したがって、一本調子の演技はどうしても見劣りがしてしまう。祭太鼓を起用に打つシーンはご愛嬌ながら、流石にうまかったが、本筋にはあまり関係がない。
何とも中途半端な仕上がりになってしまっているのは、残念でならない。前田監督は以後コミカルな路線へ舵を切って、佳作を送り出しているのは周知の通り。

↧
↧
ガードナーのブリテン作品集
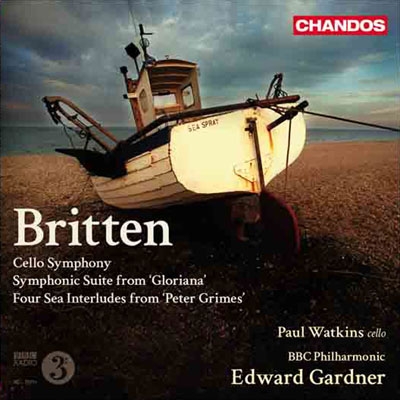
【曲目】
ブリテン:
歌劇《グロリアーナ》より 交響組曲 Op.53a *
チェロ交響曲 Op.68 #
歌劇《ピーター・グライムズ》より 4つの海の間奏曲 Op.33a
【演奏】
エドワード・ガードナー(指揮)、BBCフィルハーモニック
ロバート・マレイ(テノール)*
ポール・ワトキンス(チェロ)#
【録音】
2010年7月14-15日 マンチェスター新放送センター・スタジオ7(イギリス)
ブリテン:
歌劇《グロリアーナ》より 交響組曲 Op.53a *
チェロ交響曲 Op.68 #
歌劇《ピーター・グライムズ》より 4つの海の間奏曲 Op.33a
【演奏】
エドワード・ガードナー(指揮)、BBCフィルハーモニック
ロバート・マレイ(テノール)*
ポール・ワトキンス(チェロ)#
【録音】
2010年7月14-15日 マンチェスター新放送センター・スタジオ7(イギリス)
↧
ハンス・クナッパーツブッシュ

以前、この指揮者の評伝を読んだことがあった。その本は指揮活動に焦点はあてていたが、録音評は一切なかった。彼はチェリビダッケほどの徹底した録音嫌いではなかったが、録音という営みにかなり非協力的な指揮者ではあった。
本領はコンサートであり、一度も来日はしていないので、我々は録音などにどうしても頼るしかない。それでもライヴ録音が発掘されたり、中にはコンサート映像が出てきたりして、魅了される人は多い。遅いテンポでしかも一旦始まるとずっとそのテンポを保持してゆくところなどは、何か動かない大きな存在を感じさせるのである。
上の写真はVPOとの録音風景であろうか。中にはポピュラーな小品まで録音しているが、その中に十八番があったりする。またチャイコフスキーのバレエ音楽「くるみ割り人形」はとても好きだったとも伝えられている。ワーグナーやブルックナーだけでは当然ない。評判のブルックナーは今は滅多に演奏されない改訂版で演奏していた。今更新しく出版された原典版をやるつもりなどないというのは、この人らしい頑固な一面を示すもので面白い。
↧
はだかっ子(東映東京1961年)
![はだかっ子 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/511xHMBBLZL.jpg)
田坂具隆監督が1961年に発表した作品。大作「親鸞」二部作のあとに作られたもので、この次は「五番町夕霧楼」という有名な作品が続く。
1956年5月から9月あたり時代の埼玉県の入間地区が舞台と思われる。基地に隣接しているからだ。そして、始終戦闘機の訓練する音を聞きながら、生活している人たちが登場する。もう戦後は終わったと経済白書でも言われた頃だが、まだ戦争の傷は鮮明に残っている。主人公は母と二人暮らし。父親は召集されて、インドネシアで戦死。父親の弟弟子の大工の夫婦の二階に間借りをしている。そういう背景に貧困、差別それに教育問題が子供の視点で描かれている。単なる教育的な児童映画ではない。深刻な問題がさりげなく出てくるので、余計に考えさせられる。学校の後援会長が実は暴力団の親分だったりするし、姉が米兵と結婚して白い眼で周囲から見られている女の子がいたりする。中には病弱で亡くなる子もいて、なかなか盛りだくさんだ。しかし、もっとも愛する母親とこの子は死別してしまう。その死を受け入れまいと泣くのをこらえる子に世間は薄情な子だ、不良だとこれまた白眼視する。この子の担任の先生の父親も教育者で、大人の独りよがりの愛情は子供には迷惑、そっと見守るべき。この子が思い切り泣けるのはいつなのか、それが来ないのは、彼にとっては不幸であり、立つ瀬がなく無残ではないかというシーンは教育の難しさを突いている。結局の近所にあるユネスコ村にあるインドネシアの家がこの子の拠り所。父親が戦死して骨がまだ残っているであろう国の家を模したものだが、幸いにもこの子はそこで泣いていたのである。
主人公の伊藤敏孝は当時は有名な子役だった。長じても役者を続けていたが、脇に回ることが多かった。東映のヤクザ映画に出たり、「音はつらいよ寅次郎かもめ歌」では夜間中学の先生、「あゝ野麦峠新緑篇」では検番などで出ていた。
こういう映画でも137分という長尺ものではあったが、だれることなく観ることができた。
↧

