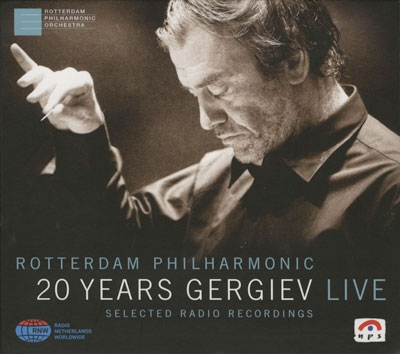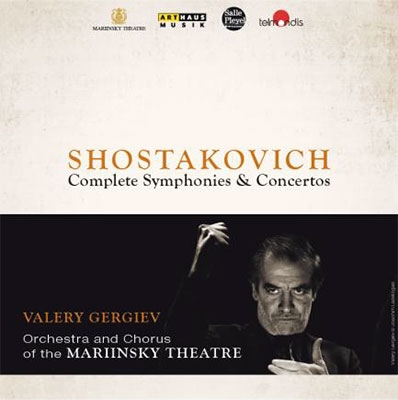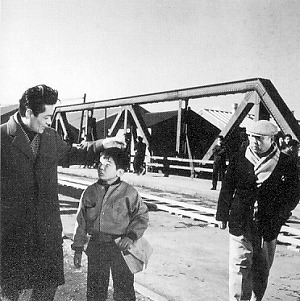【SACD収録情報】[76:01]
● デトレフ・グラナート:フレネシア(2013) 世界初演
シャン・ジャン[張弦](指揮)
収録時期:2014年1月23&24日(ライヴ)
2013年の生誕150周年を迎えて、楽団ゆかりのリヒャルト・シュトラウスにコンセルトヘボウ管として敬意を表すいっぽう、グラナート曰く真摯な意味で「アンチ英雄の生涯」と理解してほしいと述べているように、対極のスタンスをなす作品というところがユニークで刺激的。演奏時間15分47秒。
4フルート(うち3,4番はピッコロ持替)、2オーボエ、コーラングレ(イングリッシュ・ホルン)、2クラリネット、バス・クラリネット、2ファゴット(バスーン)、コントラ・ファゴット(ダブル・バスーン)、4ホルン、3トランペット、3トロンボーン、1チューバ、ティンパニ、打楽器(4人)[:アンティークシンバル、グロッケンシュピール、チューブラー・ベル、マリンバ、ゴング、4テンプル・ブロック、2ボンゴ(エンブラ(ラージ)、マッチョ(スモール))、アンヴィル(金床)、サスペンデッド・シンバル、シズル・シンバル、クラッシュ・シンバル(合わせシンバル)、タム・タム(大)、サイド(スネア)・ドラム(小太鼓)、バス・ドラム(大太鼓)]、2ハープ、チェレスタ、弦楽器群。
● ミシェル・ヴァン・デル・アー:ヴァイオリン協奏曲(2014) 世界初演
ジャニーヌ・ヤンセン(ヴァイオリン)
ロイヤル・コンセルトへボウ管弦楽団
ウラディーミル・ユロフスキ(指揮)
収録時期:2014年11月6&7日(ライヴ)
収録場所:アムステルダム、コンセルトへボウ
「ジャニーヌ・ヤンセンとコンセルトヘボウ管との組み合わせは、わたしにとってドリーム・チームのようなもの」と語るヴァン・デル・アーのヴァイオリン協奏曲は、その彼女のための、そしてまた、2011年以来レジデンス・コンポーザーを務めるコンセルトヘボウ管委嘱シリーズの一環でもある2014年の最新作。抽象的な第1楽章、より単刀直入で旋律的な第2楽章、そして急速のフィナーレからなる伝統的な3楽章の形式を踏襲しつつ、ヤンセンに特徴的な“アップ・フロント”奏法を表現しようと趣向を凝らした力作とのことで、本アルバム屈指の聴きものといえます。演奏時間25分。
1フルート、1オーボエ、1クラリネット、バス・クラリネット、1ファゴット、コントラ・ファゴット、4ホルン、2トランペット、2トロンボーン、1チューバ、打楽器(3人)、ハープ、弦楽器群(12:第1ヴァイオリン、12:第2ヴァイオリン、10:ヴィオラ、8:チェロ、6:コントラバス)
● ルク・ブレヴァイス:交響曲第6番(1999-2000)
ロイヤル・コンセルトへボウ管弦楽団
デイヴィッド・ロバートソン(指揮)
収録時期:2014年12月12日(ライヴ)
収録場所:アムステルダム、コンセルトへボウ
● ルク・ブレヴァイス:アロング・ザ・ショアーズ・オブ・ローン(2004-2005)
オットー・タウスク(指揮)
ロイヤル・コンセルトへボウ管弦楽団
収録時期:2012年12月14日(ライヴ)
収録場所:アムステルダム、コンセルトへボウ
1959年ベルギーのモルツェル生まれ、ブリュッセル王立音楽院出身で、アンドレ・ラポルテ、フランコ・ドナトーニ、ブライアン・ファーニホウに作曲を師事したルク・ブレヴァイス。いずれも世界初録音、こちらは当シリーズの常連で、アメリカの実力派ロバートソンと、1970年ユトレヒト生まれで、2004年から2006年にかけて、ゲルギエフのもとでロッテルダム・フィルのアシスタント・コンダクターを務めたタウスクのふたりが、それぞれ指揮を務めています。
[アロング・ザ・ショアーズ・オブ・ローン]
ピッコロ、フルート、オーボエ、コーラングレ、クラリネット、バス・クラリネット(クラリネット持替)、2ファゴット、2ホルン、2トランペット、打楽器(2人)、10:第1ヴァイオリン、8:第2ヴァイオリン、6:ヴィオラ、6:チェロ、4:コントラバス(少なくとも2挺はC線のある、もしくはE線をC音の線に下げた楽器を用いる)演奏時間13分12秒
[交響曲第6番]
管弦楽とライヴ・エレクトロニク。ライヴ・エレクトロニク・エンジニア:クレア・ギャラガー。演奏時間 22分42秒
SACD Hybrid
CD STEREO/ SACD STEREO/ SACD 5.0 SURROUND
【DVD収録情報】[30:27]
● ルイ・アンドリーセン:ミステリエン[Version No. 1](2013) 世界初演
ロイヤル・コンセルトへボウ管弦楽団
マリス・ヤンソンス(指揮)
収録時期:2013年11月3日(ライヴ)
収録場所:アムステルダム、コンセルトへボウ
中世の神秘思想家トマス・ア・ケンピスの著した書物に由来するタイトルを持ち、6楽章からなる演奏時間30分ほどの作品は、45年に及ぶアンドリーセンの作曲活動初の大編成のオーケストラ曲で、アムステルダムのコンセルトヘボウならびにロイヤル・コンセルトヘボウ管創設125周年記念のために委嘱されたもの。これはその記念演奏会を飾る歴史的ドキュメントで、独特の色彩的な内容は美観表現に長けたヤンソンスの腕前が愉しみなところでもあります。
3フルート(1、2番はピッコロ、3番はアルト・フルート持替)、3オーボエ、ソプラニーノ・サックス、2クラリネット(1番は変ホ管、2番は、50セント低く、自由にチューニングされた変ロ管)、バス・クラリネット、コントラバス・クラリネット、4ホルン、3トランペット、3トロンボーン、1チューバ、打楽器(2人)[:グロッケンシュピールを付けて拡張されたヴィブラフォーン、チューブラー・ベル、マリンバ、ゴング、ティンパニ(ロートトム)、2鐘(小)、クラッシュ・シンバル(合わせシンバル)、サイド(スネア)・ドラム(小太鼓)、バス・ドラム(大太鼓)、2ブレーキ・ドラム、調音されたベル・プレート群、2チャイム]、3ハープ(演奏者2人)、2ピアノ、弦楽器群(最大/8:第1ヴァイオリン、8:第2ヴァイオリン、6:ヴィオラ、6:チェロ、4:コントラバス)
画面:カラー、NTSC 16 : 9
音声: LPCM ステレオ / ドルビー・デジタル 5.0
アムステルダム・コンセrトヘボウ管弦楽団の現代音楽のアルバム。タイトルにあるようい第6集というが、その前までは今のところ手が廻らない。このオーケストラが演奏すという「信用」だけで、手に取ったもので、全て未知との遭遇なのである。幸いに通販の欄に、概要と楽器編成が載っていたので、そのまま転載した。ただ、厄介なのは実際のリーフレットにある曲順と録音の曲順がどうも違うようである。CD後半のブレヴァイスの2曲はどうも逆に記載されているようだ。その真偽の確認のしようがないのだ。長さとエレクトロニクスの使用の有無で、かろうじて判断するしかないようだ。
どれも掴みどころのない音楽で、度々聴くということにはならないが、最後のアンドリーセンの曲は映像付なので、興味深く鑑賞できた。まず、弦楽器もプルト数は通常の半分のようだし、両翼にピアノがあるのも特徴だ。金管の配置もトランペト、トロンボーン、テューバの後ろにホルンが座っているし、ファゴットを欠く木管があり、ソプラノ・サックスやコントラバス・クラリネットといった吹奏楽では時々使用するも普段管弦楽にはあまり使わない楽器を使っているのが面白い。この音源はヤンソンスBOXにも使われているようである。